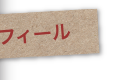■ 避難所の弁当
1995年1月17日に発生した大規模地震による災害は、後に、阪神淡路大震災と名付けられた。
地震の直後から被災地には全国から若者を中心にした大勢のボランティアが続々とやってきた。このことはメディアを通じて広く伝えられ「いまどきの若者も捨てたものではないな」という評価と同時に、ボランティアの何たるかをわきまえない自己中心的ないまどきの若者、という評価が相半ばしたのだった。
1995年2月初旬、大阪市東淀川区の区役所の中にある「青年会」の事務局に、豊中市の職員から電話がかかってきた。受話器を取った会長に電話の相手は次のような苦情を伝えたのだった。
「先日、豊中市の避難所に来たおたくの人たちが被災者のための弁当を食べていったそうですな。それがどんなに非常識なことか分かってるんでしょうね。これからは気をつけてくださいよ。よろしいな」
電話を受けた会長は、相手の居丈高な口調に気圧されて、「ご迷惑をおかけして、すみません」と繰り返すばかりだった。
やっぱり、あそこで弁当を食べるべきではなかったのだ……と、電話の声を聞きながら彼女自身もホゾをかんでいたのだった。
彼女は、さっそく次のミーティングで、その苦情電話のことを報告し、やはり食べて帰らんほうがよかったんちがうやろか、と付け加えた。彼女も他のメンバーも、あのとき、弁当を食べることをためらったのだった。
だのに、仲間の一人が食べていくことを強く主張したので、なんとなくその場の空気が弁当を食べるほうに傾いたのだった。だからこのミーティングでも彼ひとりがムキになって反論し、しまいに「ぼくらは間違ってなんかないで、あの状況で弁当食べたことをけしからんと言うてるのは誰やねん。ぼくらは被災した人らのために行ったんやで。ほかのボランティアと折り合いつけに行ったんとちがうやろ」と、声を荒げるほどだったという。
弁当ひとつをめぐって、青年会のミーティングは白熱したのだという。そして実は、各地の避難所でも似たような「問題」が、大真面目な議題として議論されていたのである。
この話を聞いて、私は、被災者と援助者との関係性のありようを端的に象徴する興味深いエピソードだと思った。
これはまた「正しい避難所(の運営)」「正しいボランティア(の行動)」「正しい被災者(の姿勢)」など非日常の混沌の中で何が「正解」かを模索する人々の○×型思考のありようを、はからずも浮彫にするものとして、面白い。
豊中の避難所でただひとり弁当を食べていこうと主張した生田浩(30歳・フリーカメラマン)に会って話を聞いた。地震から2週間ほどだった頃だった。彼の所属する東淀川区の「青年会」でも、被災者援助のボランティア活動をしようということになった。神戸・芦屋・西宮・宝塚・淡路島など兵庫県の被災地には他大勢の人が出かけているし、自分たちは大阪のグループなので、大阪府下でもっとも被害の大きかった豊中氏の庄内地区へ行こうと決まった。
自分たちはどんなことができるのか、どんなことが必要とされているのか見通しを立てるために、2月になってすぐ、6人ほどの先遺グループが、避難所になっている庄内の中学校の体育館に出かけていった。
体育館には、4、50世帯分くらいの布団が敷かれていたが、昼間ということもあり、居た人は50人くらいだった。一緒に行った人たちは、避難所の現実を目のあたりにして、びっくりした様子。こんなに酷いことになっていようとは思わなかったと、立ちすくむほどだった。
「何かすることはありませんか?」
現場を仕切っているボランティアらしい女性にたずねると、「いまのところは、ありません」というので、みんなは、じゃあ体育館の中で使うスリッパでも買いに行こうか、と近くの商店街に出かけて行った。近くで買い物ができたのである。
「物を運ぶだけがボランティアじゃないし、ぼくは残っておばあさんの話相手になることにしたのです」
生田は、神戸市須磨区の自宅で被災し、家が半壊したため、妹一家の家に避難している身だった。彼の現在の自宅は須磨にあるのだが、以前大阪に住んでいた関係で、この東淀川区の青年会に所属しているのである。
地震後2週間は、妹の子ども(つまり姪)のミルクやおむつを買うために大阪まで(阪神も阪急もJRも不通だったので西宮まで30キロは歩いて)1日がかりで出かけたり、友人たちのいる長田の避難所で手伝いをしたり、カメラマンという仕事がら、港湾施設や街の被災現場の記録写真を撮影するために歩き回っていた。神戸の避難所には千人単位の人びとがひしめきあっていた。学校では、体育館のみならず全ての教室、廊下にまで人があふれ、校庭のテント生活を余儀なくされる人もたくさんいることを、彼は肌身で知っていた。そこでは、水洗便所は使えず暖房もなく、しばらくは電気でさえとだえたままだった。
それにくらべれば、この豊中の避難所は、余裕があるように見えた。
この体育館で暮らす人びとは最大に見積もっても200人ほどなので、スペースにも余裕があり、暖房用の石油ストーブが10台ほども置いてあるのには驚いた。テレビも置いてあった。自宅から電気こたつを持ちこんでいる人も。タオルをぶらさげて、「ええ湯やった」と言いながらさっぱりした顔で避難所に帰ってくる人もいて……。
後日発表された集計結果によれば、災害救助法によって設置された避難所の数は、豊中市では震災直後のピーク時で68ヶ所、避難者は約3千800人だった。それに対して神戸市では、599ヶ所に約22万人(うち最多の東灘区では6万5千人)が避難したという。これも後で知ったことだが、自治体を通じて支給された弁当も同法にもとづいて国費でまかなわれたらしい。
兵庫県全体の避難者の数は約31万7千人だったのに、隣の大阪府では豊中市の3千800人と大阪市の300人。
この違いが余裕の有無につながり、イメージの違いにつながったとも言える。
しかし、なにごともひとつの規準で一律に考えないほうがいい。今度の震災でもそのことが痛感された。
神戸市内の被害は甚大だったのに、たとえば、道路1本、鉄道1本はさんで片側の家はペシャンコ、反対側は何ともなしという状況がそこここに見られた。テレビは、その被害甚大な、いかにも「被災地」らしい方の光景を選んで放送し続けたのだった。やがて、その光景が「あるべき被災地」(あるいは「正しい被災地」)のモデルと化していったのである。
洲本に住む友人のところには、淡路島が震源地だというニュースに驚いて安否を尋ねる電話や手紙、水や食料、現金などが次々と届き、「自分のところは大丈夫だからと言っても信用してもらえないので難儀しているのや」と、遠方の友人たちの反応にとまどっているのが興味深かった。震源地の北淡町の被害は甚大だったが、洲本市の彼の家では何の被害もなかったのだという。だのに、世間には、淡路島=震源地=被害甚大、の画一的なイメージがひろまった。一方で、阪神・淡路大震災=兵庫県が被災=大阪府は無事、の画一的イメージもまた強まった。
そしてその背後に、被害の軽重が(報道)価値の軽重にスリ換えられていく。極端に言えば、死者の数や倒壊家屋の数、被災者の数を競いあうという、おぞましい現象さえも現れたのである。だから、「被災地」のなかでも被害軽微な地区は「亜流」被災地と見なされやすく「当局者」たちは肩身がせまい。肩身の狭いのは不快だから、被災地ではなかったと思いたいとの思いと、どうせ被災地になったのなら神戸に負けない「立派な被災地」になりたいという思いがせめぎあうことになる。
援助する側も同様だ。援助する以上、「正しい」援助者でありたい。メディアが伝える被災地は、水や食料衣料、医薬品など第一次的な物的援助を緊急に必要とする地域である。だから、あの「にぎり飯を小包で送ったひと」たちも、実は、それを必要とする「正しい被災地」に向けた「正しい援助者」でありたかったのにちがいない。「正しい」×「正しい」=「正しい」二乗=「とん珍漢」という皮肉な現象が随所に頻出したのである。
生田浩と仲間たちが訪れた豊中市の庄内地区の避難所で時を過ごすうちに、いよいよ夕食の時刻になった。体育館に運ばれてきた弁当を、ひとつずつ避難者の手元まで配ってくださいとの指示が出た。生田は、「ええ、そこまでするのか」と思ったが、これもここに余裕があるからだろうと納得して、この避難所を仕切っているらしいボランティアの女性の指示に従った。ほかにも、石油ストーブの燃料の残量をチェックして灯油を注ぎたすという神戸では考えられない作業も当然のこととして指示された。
弁当は多めに運ばれてくるので、いつも余るのだという。この体育館のある学校の先生らしい人も「余らせてもいたむだけですからもったいないし、せっかくだから皆さんも食べていってください」と、すすめてくれた。
それまで話し込んで親しくなった高齢のおばあさんたちも、「いっしょに食べていけ」と誘ってくれたので、生田は、ここで食べることにした。殺風景な体育館の中に居るのは、4、50人だったので皆でしゃべりながら、にぎやかに食べていくのが良いだろうとの判断だった。
だのに、仲間たちは「とんでもない」といって辞退した。この弁当は(気の毒な)避難者のためのものだから(正しい援助者としての)私たちボランティアがそれを食べるのは「×」である――というのが彼らの判断だった。新聞やテレビで流される神戸発のニュースにも、「避難所の弁当を食べていく不届きなボランティア」というのがあって、やはり、「○」のボランティアはそんなことはしないものだ、というのが一般的な正解であることくらい彼は承知の上だ。
しかし生田は、あえてこう反論したのだった。
「ここは長田や東灘の避難所ではないんやで。弁当は沢山あるやないか。おばあちゃんたちも誘ってくれてるやんか。それなのに断ったら、かえって気を悪くするかも知れへんで。〝ああそうか、こんなところで年寄り相手に冷えた弁当なんか食われへんの? あんたら、家に帰ったら温かい晩ごはんあるもんな〟て思われても仕方ないで。それに、せっかくの弁当が余っても、もったいないやろ」
結局、生田の〝主張〟によって、いっしょに食べていこうかということになった。おばあさんたちと車座になって、四方山話をしながら時を過ごし、じゃ、またねと言って別れる時、地震で頭をぶつけてコブをつくったというおばあさんが、「ほんまに、おおきに」と、何度も繰り返して喜んでくれた。
そのおばあさんの顔を見て、生田は、ああよかったな、と思ったという。
帰りの電車の中で、一緒に行った女の子が、「でも、たまらんかったわ」と溜息をつくのだった。仕切り役の女性ボランティアからチクチクと皮肉を言われ続けたのだそうだった。
「ここでは、ボランティアがすべてのお世話をしてるんよ。でも、あんたらエエ気なもんやね、仕事のない時間帯だけ来て……」
そして、その3日後、彼らの事務所に冒頭の苦情電話がかかってきたというわけだ。
弁当ひとつで大騒ぎになったのは、彼らのグループだけではなかった。
実は、豊中市の職員のなかでもそれは〝大きな〟課題になっていたらしい。
当時、市役所では、例によって頻繁に会議が開かれていた。会議、会議、会議……。次ぎから次ぎへと判断すべき課題が出現し、幹部たちが寄って会議が開かれる。非常時の出来事に平時のルーティンワークで対応しようとするところに無理があることは分かっているにもかかわらず、なまじ〝余裕〟があるだけに、現場職員の判断と裁量にゆだねられることは少なかった。大地震による災害対策という仕事は誰にとっても初めての体験だった。公務員にとって、先例のない課題を短時間に処理することほど難儀なことはないだろう。しかも、マスメディアを通じて全市民はおろか全国民が注目している時期に、チョンボを犯すわけにはいかない。「正しい公務員」には「正しい判断・対処」が求められているのである。責任あるポストの管理職たちの「間違い忌避症」は、深刻だった。まったく、危機に瀕しているのは自分の立場なのだった。
会議は長引き、結論は出にくい。食事も必要になってくる。
避難所で余る弁当の処分も頭の痛い問題だった。避難所の人口は流動的なので、人数ピッタリの弁当を手配するのはほとんど不可能だ。だから、多めに配る。その上、ボランティアが温かい食事を炊き出ししたり、外出した人が外で食べてくるようになるので、当然余りがでる。余ったからといって翌日にまわすわけにもいかないだろう。食中毒でも起こしたら大変だ。だったら、廃棄処分するしかない。
現場のジレンマだ。
だれが考えても捨てるのはもったいないので、役所の会議参加者のための弁当として活用したらどうかと思いつく者がいるのも当然の成り行きだろう。……が、ことはそうすんなりとは運ばない。会議の席上に弁当が届けられると、たちまち、次のような異議申立があった。「ちょっと待て。これは避難所の人たちのものやないか。その弁当をわれわれが食べるのはスジが違う。流用してはならん」
この意見は正論である。市民のために用意されたものを市の職員が〝つまみ食い〟するのは、明らかに「×」に決まっている。
だとすれば、余った弁当は、みすみす捨てた上で別会計で会議用の弁当をあつらえる方が適切な判断なのか、それこそ税金の無駄使いというものではないか。
会議は、本来の議題を検討する前に、この弁当を食うべきか食わざるべきか、変則的で流動的な状況の渦中で、「正しい公務員」としての「正しい判断」はいかにあるべきか、ここでも、弁当を巡って会議はえんえんと続くのだった。
災害対策本部に限らず、時間外勤務が急増し泊り込みの職員も多かったが、豊中市の職員は時間外手当てがきっちりと支給され、月給が倍増した職員も多かった。「非常時なので」部課長など管理職にも支給されたらしい。
ちなみに、西宮市でも職員には時間外勤務手当がきっちり支給されたが、管理職には平時と同様支給はなかった。泊り込む者への手当を「宿直手当」とするか「深夜勤務手当」とするかの議論はあったが、結局後者として支給されることになった。神戸市の場合も時間外手当は支給されたという。
対策会議では、こんな議題もあった。
2月、ある大手の寿司メーカーから、節分の日に巻き寿司を避難所の皆さんに差し上げたいとの申し入れがあり、これを受け入れるかどうか議論された。
市外の工場から、閉店後に交通渋滞の中を届けると、午後10時ころになるという。すべての避難所に公平に分配するためには何本必要かを見積る作業も大変だったが、午後10時過ぎまで受け取りと分配(たったそれだけ)のために人出を残しておかなければならないのが問題だった。何人残らせるのか、それは誰だれか。それよりも、翌日に、ルーティンワークのなかで作業したらどうかとの意見に対しては、「そんなことしたら、前日の売れ残りを食わすのかと苦情がでるかもしれない」との心配が表明され、「それもそうですな」。
またまた例によって会議は堂々巡りをはじめるのであった。わたしが責任をとりましょう――というひと声が出ない。「正しい公務員」は個人の責任において判断したりしない。
その一方で、避難所に冷蔵庫を置いてはあかん、という断固とした判断をゆずらない管理者もいたのだった。
その避難所は国庫の補助金を使って建てられた社会教育施設だったため、細かい規則が定められており(もちろん震災前から)、現場の管理者はその管理マニュアルを遵守することこそが「○」というわけだ。この施設には公費で購入した備品以外の物を置いてはいけない――との制約がついていた。そのココロは、公平な利用を保障するために特定の個人やグループの私物を置くことでスペースを占有し私物化されるのを防ごうというものだ。公共の施設を特定の個人・グループが占有・私物化してはならない――のは当然だろう。
しかし、いまは、震災の被災者が避難するシェルターとなっているのである。
対策本部からは、弁当を残したらあかんと、うるさく言ってきている。とにかく食中毒を出すのが怖いからだ。でも、避難所での生活を余儀なくされている人たちは、支給されている弁当以外にも食べ物や飲み物を身近に置いておきたい。
ほかの避難所では、かしいだ自宅から冷蔵庫を運び出してきて利用している所もあることを知った人たちが、自分たちも家から冷蔵庫を持ってきてここに置きたい、というわけだ。非日常の生活空間の中に、なんとか日常性を取り込みたいとの願いでもある。
しかし、件の管理者は先のマニュアルを根拠に、アカン! との主張を変えなかった。
「わしが責任をとるんやで。アカンもんはアカンのや」
「(非常時における)正しい避難所の使い方」というよりも「(平時における)正しい公的施設の使い方」の原則が貫かれたのである。
では、施設の中には入れずに軒下に置くのはどうやろうと、折衷案も出たが、彼は首をたてには振らなかったという。彼は判断したくなかったのだろう。この施設が避難所になったのは、自分の責任ではない。自分の責任範囲はこの施設の管理責任者として、地震があろうとなかろうと、以前から金科玉条としてきた規則を墨守することである。