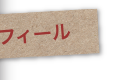砲撃中の大砲のかたわらですやすや昼寝する赤ん坊 M16ライフルをおもちゃにして遊ぶ子どもたち 機銃掃射をあびながら笑いころげる兵士たち ポルポト派の攻撃によって陥落寸前のプノンペンと その郊外の前線で見聞きした〝不思議な戦争〟 |
 |
|
|---|---|
|
1991年1月17日にはじまった「湾岸戦争」。開戦以来、多国籍軍の空爆にさらされるバグダットの夜空を衛星中継しつづけたCNNの映像や、標的に突っ込んで行くスマート爆弾の弾頭につけたテレビカメラが送ってきた映像などに象徴されるように、この戦争は「テレビで実況中継された最初の戦争」とか「ショーアップ・ウォー」とかと呼ばれる、妙な戦争だった。例のCNNのピーター・アネットがやった戦争の実況放送は世界の105ヶ国に中継されたという。
文字通り〈テレビ観戦〉をしていた身には、すでに多くの人が言ったり書いたりしているように、「ほんものの戦争」という実感がともなわず、ともすればコンピュータゲームと錯覚してしまいそうな「戦争」だった。
徹底的な報道管制が敷かれ、血なまぐさい映像がほとんど流されなかったこともあってのことだろう――と、これも多くの〝評論家〟たちが指摘しているところだが、「ペンタゴンは、今回はベトナムの教訓を生かした」のだということになっている。アメリカには、ベトナムで負けたのはジャーナリズムのせいだと信じている将軍たちが大勢いるらしい。
たしかに「ベトナム戦争」では、アメリカ人に限らず多くの記者やカメラマンが前線に出かけていった。彼らの従軍取材を受け入れ「報道の自由」を保障するために、軍の指揮官たちが大いに便宜をはかってきたことは、いくつかのルポを読んでみればよくわかる(たとえば石川文洋『戦場カメラマン』朝日文庫)。そして彼らジャーナリストが送ってきたおびただしい記事や写真の中には、血と死の嗅いが強くただよい、受け手の感性に戦争の「悲惨」と「愚かしさ」を訴える調子のものがきわだっていたのだった。それらの記事や写真が、アメリカ人をはじめに世界の気分と反戦気運を醸成し、「アメリカ敗退」を実現してしまった――というわけだ。
あれから15年。ベトナムでは敵に敗けたのではない、世論に敗けたのだ、と考えるペンタゴンの将軍たち――今度は「うまくやった」らしい。
そういえば、ベトナム戦争は「宣戦布告のない戦争」とも呼ばれていたのを思い出す。あるいは、東西(米ソ)冷戦構造下の「代理戦争」とも。植民地時代に根をもつ「内戦」に〝世界の警察官〟アメリカ合衆国が干渉し、やがて直接軍事介入することでズルズルと戦闘がエスカレートし泥沼にはまっていった過程については、すでにあまたのドキュメントによって広く知られている。
しかし、「ベトナム戦争」の戦火は、南北ベトナムにとどまらず〝国境〟を越えてラオスとカンボジアにも及び、いわゆるインドシナ三国全域が〝戦場〟と化した戦争であったことを知る人は、案外多くないようだ。
カンボジアが戦場と化したのは1970年。シアヌーク殿下が国家元首として〝仏教社会主義〟などとも呼ばれる独自のスタンスで政権を維持してきたが、1970年、殿下がパリの訪問中にクーデターが起こり殿下追放が決議された。国名も、カンボジア王国から「クメール共和国」と改称され、元首相のロン・ノル将軍が大統領に就任した。そうした政変を待ちかねていたかのように南ベトナム軍とアメリカ軍が国境を越えてカンボジア領内に侵攻し、戦火は一気に広がった。北ベトナムから正規軍が南下するルートおよび南ベトナム民族解放戦線(俗にベトコンと呼ばれた)への補給ルート(ホーチミンルート)がカンボジア領内を通って南ベトナムの山岳地帯に通じている(映画『プラトーン』の舞台がその山岳地帯だった)、そのことを知りながらシアヌーク殿下は黙認している――とするアメリカ=南ベトナム政府軍は、何としてもその〝聖域〟への直接攻撃をはかりたかったわけだ。その意味でこのクーデター(親米政権の誕生)は〝おあつらえ向き〟だったと言える。
この政変後、プノンペン新政権の承認をとりつけたアメリカはB-52の編隊を越境させてカンボジア平原の爆撃を実行し73年の8月まで続けたが、結局、ルートをつぶすことはできなかった。
一方、追放されたシアヌーク殿下は北京に亡命し、ロン・ノル政権に対抗する勢力をまとめゲリラ戦を指揮するなど目立った動きを見せていた。その結果、カンボジアも内戦状態に陥ったが、当時、マスメディアを通じてぼくたちが理解していたのは、「親米政権のロンノル大統領」対「祖国回復を図るシアヌーク殿下」という単純な図式の見方だった。反政府勢力のゲリラは「クメール・ルージュ(赤いクメール)」と呼ばれていたが、彼らはシアヌーク殿下の指導の下にあると、ぼくたちだけでなく多くの人が見ていたはずだ。だから、アメリカ=ベトナムが手を引きクメール・ルージュがプノンペンを〝解放〟すれば、昔の暮らしが戻ってくるものと、〝評論家〟たちだけでなくプノンペン市民の多くも楽観していたふしがある。しかし、その見通しがかなりゆがんでいたことは、75年のプノンペン〝解放〟後のなりゆき(ポルポト派、キリングフィールド、ベトナム介入、ヘンサムリン政権…)を見れば明らかだろう。70年以来、20年越しの内戦状態は今や常態となり、和平会議の開催さえままならないでいる。
カンボジアの内戦がはじまってから(当時はカンボジア紛争とも呼ばれたが)、ぼくは、隣国(ベトナム)の都合、ひいては大国(米ソ)の都合で戦争にひきずり込まれてしまった小さな国のことが気になっていて、その成り行きに強い関心を抱いているところだった。報道の量もベトナムに較べれば少なく、ベトナムは〝メジャー〟、カンボジアは〝マイナー〟だった。ベトナム戦争反対運動はあっても、カンボジアのそれは、知らない。そもそも「カンボジア戦争」という呼び方に、なじみがないのだろう。
新聞をめくりながら、ぼくはそんな釈然としない気持ちをもてあましていた。
報道によれば、やがて、ベトナムから米軍の撤退がはじまり、カンボジアではクメール・ルージュがほぼ全土を〝解放〟、ロンノル政府軍は陸の孤島と化したいくつかの大都市をアメリカの全面的な援助(1日当り100万ドルと言われた)にたよってかろうじて維持している――という様子が伝えられてきた。首都プノンペンも、政府軍のテリトリーは都心から半径20キロの範囲に閉じこめられ、市内の到るところにロケット弾が打ち込まれるほどに切迫、プノンペンの陥落は時間の問題だというのが、マス・メディアで見る限り、大方の見方だった。
そんな折りも折り、「プノンペンの街から犬が消えた……」という内容の記事が、毎日新聞の外信面に載った。
日付けをわすれたので引用することができないが、その内容は、およそ次のようなものだったと思う。
戦場となった田園地帯から戦火を逃れて避難する人が大量にプノンペンに流れ込んだことによって首都の人口は倍増し200万人を越えた。農業はストップし人口は倍増。ということになれば当然それだけの人口をまかなうための食糧が不足する。アメリカが輸送機を往復させてタイから米を運び込んでいるものの、ひもじい思いの人はふえるばかり。彼らは、犬まで食べてタンパク源にしている。そしてとうとう街から犬が姿を消した――ざっと、そんな調子の記事だったが、読み手の印象としては、ああ、いよいよそこまで切羽つまっているのか、食うにこと欠いて、食べているのか……と、深刻な印象だった。
ぼくは、その記事を見て、プノンペンに行くことを決めたのだった。
別に目的らしいものはなかったが、ロケット弾の飛び込んでくる街の庶民の暮らしの中に身をおいてみたいとの思いが強くあった。
1974年の春。26歳だった。
ビザは、「観光」で申請するしかないだろう。
それまで何度か外国に出かけたことはあったが、ビザは自分で申請することにしていた。しかし、こんな時期に「観光ビザ」が発給されるだろうか――東京の大使館に出向く手間を省くために旅行代理店の友人に相談すると、彼も首をかしげている。ダメでもともと、ものはためし。彼に申請をたのんだら、意外にもビザはすんなり発給された。
雨期に入ると戦闘が下火になるのがこれまでの例だったので、出発は6月、滞在は1ヶ月と決めた。
大阪―香港―サイゴン―プノンペンというのが最短ルートだが、香港―サイゴン間の航路はすでに閉鎖されていた。バンコク―プノンペン間にエール・フランスが週1便飛んでいるというのでそれを予約したものの、この航路もいつ閉鎖されるか分からないという。
反政府勢力に閉じこめられ孤立している首都にツーリストビザでほんとうに入国できるのだろうか――バンコクの安宿でコーヒーを飲みながら、まだ、半信半疑だった。ま、いいか、入国拒否されれば、された時のこと。ダメでもともと。帰りの航空券はあるんだから。
バンコクからの便はボーイング707。ぼくを入れて乗客は6人だった。フランス人らしき白人が3人と、中国系とおぼしき東洋人が2人。
――プノンペン・ポチェントン空港に着陸します……と、たぶん言っているらしい機内アナウンスで下を見ると、爆弾か砲弾の跡とおぼしき赤茶けたクレーターがちらほら見える。
と思ううちに機体がグラリと傾き、翼が地面に対して垂直になったかと思えるほどの急角度に傾いたまま旋回をはじめ、これには肝が冷えた。座席の背もたれに頭をつけたままのかっこうでも、窓の外に立ちはだかる壁のように地面が見える。ちょっと信じがたい光景だ。そのまま小さな半径でを描きながら高度を下げていく。
翼端が椰子の頭をかすめそうに見えた瞬間、機体がグイと水平に戻り、戻ったとたんにタッチダウン。滑走路のわきにある戦闘機用のと対空砲の列が窓の外を飛び去っていった。
まるでアクロバット飛行だった。手のひらは汗でびっしょりだ。いったい何事が起こったのかと心配したが、あとできくと、空港へのアプローチの際、進入路の下に入り込んだゲリラがロケット砲やライフルを射ってくるので、その射程に入らないよう高いところを飛んできて、できるだけ小さな空域の中で降りなければならないからだ、とのことだった。
 |
|
|---|---|
|
空港のターミナルは、ちょうど田舎の駅舎といった感じの小ぢんまりした建物だった。ぼく以外の乗客には全員に迎えが来ていた。タラップの下で握手したり、抱きあったりしたあと、そそくさと建物の中に消えた。独り残されたぼくは、ほんとうに入国できるのだろうかと心細さをかかえながらイミグレーションを探していると、いっしょに降りたフランス人の一人が入国手続をしているのが見えた。彼は、パスポートに紙幣を添えて係官にわたしているところだった。いやはや、ここでもが幅をきかせているのか。ぼくは数年前、インドネシアでこの〝アンダー・テーブル〟に神経を使ったことを思い出して気が重くなったが、戦争の末期的現象なら仕方ないか、妙に納得しながら〝相場〟が気になった。
彼、なんぼ払ったんやろか――フランス人の手元に目を凝らす。イミグレーションの係官は堂々と紙幣を受けとった後で、あろうことか、おつりを差し出した。金額はわからなかった。フランス人はおつりをポケットにしまうと、さっさと行ってしまった。
さて彼はいくら払ったのだろうか。の係官にたずねるわけにもいかず、ぐずぐずしていると、突然、誰かがぼくの肩をポンとたたいた。
「むにゃむにゃむにゃ……ムッシュ?」
フランス語らしい。ふりかえると、クメール人らしい青年が立っていた。
「ジュシ、ジャポネ、ネパ、フランセ」(わし日本人じゃけんね、フランス語わからん――と答えたつもり。もちろん、クメール語もさっぱり〝わからん〟。聞いたことも見たこともない言葉だった)。
「オー、ユーア、ジャパニーズ!」
彼はころりと英語に切り換えてこう言った。
「空港からのトランスポーテーションありますか?」
ほらきた。白タクドライバー? しかし、とにかく街の様子がわかるまでは用心が肝心。慎重第一。もともとぼくは空港から街までバスで行くつもりだった。
「わたしバスで行く、ノーサンキュ」
「ええっ、バス? 冗談でしょ? バスがあると思ってる? ああ! あなたこの国を知らない。バスステーションどこにありますか」
「バスないならタクシーに乗ります」
「おお! やっぱりあなたはこの国を知らない。タクシーどこにありますか、どうぞ探してください。でも心配いりません。私トランスポーテーションあります。ホテルどこですか」
彼はそう言うなり、私のもっていた入国カードをとりあげて、滞在先の欄を読んだ。
「おお、ホテル・ル・プノン。トレビアン。リザーブしてますか?」
「ナッチェット」
出発前に大阪でプノンペンで有名なホテルを調べて、そのうちの一つを書いておいただけで、ぼくは最初からそのホテルに泊まるつもりはなかった。だからもちろん予約もしていない。
「あなたはエライ。ル・プノンは料金が高いからね。20ドル以上だよ、80ドルもある。私がもっと安くて良いホテル紹介するよ。だから早く入国手続しなさいよ」
うっかりしていた。ぼくはまだイミグレーションを通る前なのだった。もちろん、一緒に降りた客は誰も残っていない。髭の係官もカウンターの向こうの椅子に座ってお茶を飲んでいる。
――でも、どうしてこの男はイミグレーションのこちら側に来れたわけ?
考えているスキに、彼はぼくの手から入国カードとパスポートをひったくり、係官に声をかけると、空港税をたてかえて払い、あっという間に手続きをすませてくれた。賄賂も何もあったものではない。パスポートにポンと入国スタンプを押すと、はいどうぞ。
関税のカウンターは無人だったが、彼はかまわずぼくを引っ張って通り抜ける。ぼくはさすがにためらったが、誰もとがめる者はいない。要するにフリーパス。
いったいどうなっているのだろうか。
 |
|
|---|---|
|
入国管理の厳しいことを覚悟していただけに、ぼくは狐につままれたような思いで、拍子ぬけしてしまった。
先のフランス人はなぜ金を払ったのかと訊ねると、「彼はビザを買ったのです」と教えられ、ぼくはわが耳を疑った。首都の空港のイミグレーションでビザが買えるとは。空港税をとられるのはわかるけど、ビザが買えるとは……。空港から追い帰されるのを覚悟して心配しいしい来たのがアホらしくなってきた。
あとで判かったことなのだが、実はこの当時、すでに戦況は政府軍の〝負け〟が明らかになっており、兵士も警官も含めて役人はすっかり〝やる気〟を失ってしまっていたのだった。しかし、この時のぼくの目には、こうした公務員たちの士気の喪失状態と、南の国の人たちののんびりゆったりムードとの区別がついていなかったのである。
無人の税関を通り抜けると、わずか数歩でもう外に出た。
青年は、ホテルとトランスポーテーションを紹介すると言って熱心にぼくを口説き続けている。歳はぼくと同年輩。感じは悪くない。
建物の外に出て、あたりを見まわしてみても、彼の言う通り、バスターミナルらしきものもタクシー乗り場のような場所も見当たらない。
目の前の木陰に一台のメルセデス・ベンツが止まっていて、青年は、これが自分の言うトランスポーテーションだと指さしながら胸を張っている。
運転席に中国系の若者が見える。彼の友だちらしい。
乗れよ、と合図するが、やはり、はいそうですかと乗るわけにはいかない。
「ほんとに安いホテル知ってるんやろな。ぼくの欲しいのは一晩3ドルくらいやで」
「まかせなさい。あなたが気に入るまで車で一軒ずつまわります。だいじょうぶ」
「ところで、トランスポーテーションの代金はなんぼ?」
ここではたと気がついた。ぼくは、まだこの国の通貨である「リエル」をもっていなかった。当座のリエルを両替しておきたかったのと、両替の窓口で空港から街までの運賃の相場を聞いておきたかったので、建物に引きかえしたが、両替カウンターは見当たらなかった。
彼もついてきて、何を探しているのかときくので、両替したいと言うと、「わかった、あなたの必要なものわかってるから、とりあえず車に乗りましょう」
しばらく迷ったが、それまでの彼の話しぶりや顔の表情などの印象から判断して、はらを決めた。彼らに案内を頼むことにして、メルセデスの後部座席に乗り込んだ。
車が動きだすと、彼はまたしゃべりだした。助手席からシート越しにしゃべろうとして体をよじった拍子に、シャツの裾がずれて、ズボンのベルトの腹のところに大型のピストルがはさまっているのがチラリと見えた。
心臓がドキンとして、こりゃ目すったかなと思ったが、さも「そんなものは見なれとるけんね」という表情をつくりながら、さりげなく言ってみる。
「おお、ピストルもってるみたいやね」
ああ、これか? という風に彼はピストルを抜き出して、ひょいとぼくの方に見せてくれた――。コルトだのブローニングだのという種類はわからないものの、ずいぶん大型のオートマチックだった。これでズドンとやられたら即死やな、というようなことを思っているうちに、彼は、いかにも扱いなれた様子でまた腹とベルトのあいだにさし込みながら、次のような話をするのだった。
実は、この友人は商人なのだが、この戦争で身動きがとれない。今後の見通しも暗い。だから彼は香港に逃げたがっている。だから米ドルが要る。国内でドルを買うのはとても難しいので、外国人から買って貯めているところだ。そこであなたのドルを売ってやってもらえまいか――というわけだ。
公定レートなら1ドル=370リエルだが、ブラックマーケットでは1ドル700リエル。ブラックマーケットのレートで買いたいという。(ちなみに、この時ぼくは1ドル=290円でドルを買っている。前年の1973年に変動相場制に移行したばかりだった)。
どうやら、ヤミドル買いの網にかかったらしい。カモを求めて空港で網を張っていたのだろう。しかし、二対一。彼らが居直り強盗である可能性もないではないが、ぼくのカンは、〝大丈夫〟と言っている。いずれにしても両替は必要なのだから。
「オーケー、50ドルだけ売ることにしよう。ただし、ホテルが決まってから」
彼らもそれに同意して機嫌よくドライブしてくれた。
市内に入ってホテルを三軒ほどあたってみたら、3ドル50がいちばん安かったので、とりあえずここに決めた。インターナショナルホテルという名だった。リエルでの支払いはダメ、米ドルで払うなら部屋をやる、と愛想の悪いおやじが言うので、ついでに、両替のレートを訊いてみたら、1ドル=370リエルの公定レート以外では買えないという。
ホテルをここに決めるまで、嫌な顔もせずにメルセデスの2人組は面倒を見てくれた。だから約束通り、彼らの言い値でドルを売ることにした。50ドル札を差し出すと、「せめて500ドル売ってもらえないだろうか」ときた。しかし、ここは心を鬼にして、50ドルだけ3万5千リエルで売った(ひょっとしたらもっと高く買うヤミ屋があるやも知れぬ、と欲の皮がつっぱったから。案の定、あとで1ドル=800リエルのヤミドル屋を見つけた)。
プノンペンの街の第一印象は、まったく意外なことに〝平和〟そのものだった。のどかな美しい街に見えた。
この街は、かつて植民地として支配した時代にフランス人がつくったのだろう。フランスに行ったことはないが、映画やテレビや写真で見るパリの下街の感じに似ているように思う。ベランダにフランス窓、サルスベリの街路樹、歩道にまでテーブルと椅子を並べたカフェ、香ばしいフランスパンのカスクート……。ぼくの泊ることになったホテルの界隈はおそらくこの街でも多少〝お上品〟な雰囲気の地域らしかったが、カフェはいつも人であふれていた。
隣のテーブルでは若いカップルが話し込んでいるし、そのむこうでは髭の紳士がパイプをくゆらしながら新聞をひろげている……といった具合に。
こうしてぼんやりとまわりを眺めながらコーヒーを味わっていると、まったく、のんびりゆっくりと時間が流れている。この光景を見る限り、これが現に〝泥沼の内戦〟下にある街の風景とは、とても信じられない。戒厳令がしかれ、午後6時半以後は外出禁止、深夜になると郊外からロケット弾が撃ち込まれるような街なのだということが信じられないのである。
街の中心部にまぎれ込むとその〝感じ〟はいっそう強くなった。この街は、中心に巨大な中央市場を置き、そこから放射状に幹線道路が延びている――というつくりになっている。この中央市場付近のにぎわいときたら、バンコクやジャカルタ、香港の下町のさと変わるところがない。市場はに満ち、通りはホンダやヤマハ、カワサキのバイクであふれている。
食べものも、ふんだんとは言えないまでも〝欠乏〟しているようには見えない。ずらりと並んだ屋台で大勢の人がひしめきながら食事している光景からは、大阪で新聞を読んで抱いていた
〝感じ〟はまるで感じられなかった。いよいよ食糧に事欠いて犬まで食べだした――という切迫感は、ない。
もっと驚いたのは、この街に〝英語塾〟が乱立していることだった。英語ができればアメリカからの援助ラインに就ける(前線に出なくてすむ)からとの思惑から中産階層の子弟のあいだに〝英語ブーム〟が起こっているというのである。いくつかの塾をのぞいてみると、小学生向けの教室から青年向けのクラスまでいずれも熱気にあふれた繁盛ぶりだった。
そこで知り合った講師のベン・サボラス君は、近郊都市からの疎開組の一人だったが、いくつもの塾をかけもちで超多忙、ホンダスーパーカブで走りまわっている。彼は楽天的な性格のせいか、戦争の見通しをたずねても、もうすぐシアヌークがってきてロンノル一派を追い出し昔の暮しに戻れるだろうと、こっちが戸惑うほどの楽観ぶりだった。
「プノンペン市民の九割はそう思ってるよ」
彼はアパートの建物の屋上にバラックを建てて住んでいた。ゲリラに爆破されたコカコーラの工場から拾ってきたという、あの見慣れたコーク模様が一面にプリントされた裁断前の製カン用スチールシートでこしらえた〝ペントハウス〟に仮住まいしながら〝その日〟までしのいでいくよ、と彼は笑っていたが、翌年の〝プノンペン解放〟後、ポルポト派による大虐殺の嵐を生き延びることができただろうか。
彼が母親と一緒に暮らしている蒸し風呂のような〝ペントハウス〟でお茶をごちそうになりながら、ぼくは気になっていた〝犬〟のことを訊いてみた。
「えっ? 日本人は犬を食べないの? アジア人はみんな食べてると思ってたのに。そうか、日本人は犬を食べないのか――」
カンボジアでは昔から犬を食べてきたよ、と教えられて、はたと思い当たった。そういえば、香港でも台北でもソウルでも、昔から犬は食べていた。上海でも食べるときいたことがある。中国の食文化の影響の強い文化圏では、犬の肉は、食材なのだった。フランス人がウサギを食べ、日本人がクジラを食べるように。
ぼくの反応を見て、彼は思いついたことがあるらしく、「よし、いまからスナックを食べに行こう」と、立ち上がり、ぼくをバイクの後ろに乗せて走りだした。
着いたところは、トンレサップ川とメコン河が合流するあたりにつくられた大きな公園で、水面をわたる涼風を求めて大勢の市民が三々五々、のんびりと散策しテーブルにっていた。テーブルにつくと、彼は、頭の上に大きなザルを乗せた物売りの少年を手招きしてザルをテーブルの上に置くよう言いつけた。ザル一面に並んでいるのは、きれいに形を整えて串を通したと、15センチはありそうな大イナゴだった。
ベン・サボラスは、蛇を2本買って1本をぼくにくれ、食べてみろという。皮をむいたあとスパイスを効かせて乾燥したもので、小骨の多い魚の干物といった風味。ビールのあてにもってこいの珍味だった。
イナゴも同様の干物にしてあって、バリバリとかじると香ばしさが口に広がった。
うまい。彼にそう伝えると、彼は静かにこう言った。
「ぼくたちは、飢えたから仕方なくこれを食べているわけではありません」
そう言えば、かつて第二次世界大戦後の戦争裁判で、タイかビルマあたりで日本軍の捕虜になった英国兵が収容所で虐待を受けたとして責任者を告発したその理由の一つに、木の根を食わされたというのがあったが、調べてみると、彼らはゴボウを木の根と誤解していたのだった……。
いずれにしても、プノンペンの人々の暮らしぶりは、あらかじめ思い描いていたイメージとの間にかなりのギャップが実感できた。〝予想〟に反して〝のどか〟であったり、〝にぎやか〟であったりする〝平和〟な光景は、やはり不思議であった。
不思議と言えば、夕暮れ時、路上にあふれていた人の群れがアッという間にかき消えるのも不思議のひとつだろう。夜間外出禁止令による外出禁止時刻は午後6時半。夜間といっても6時半ごろはまだ明るい時刻で、その直前まで街は喧噪に満ちている。ところが6時半には人っこひとりいない無人の街路と化してしまう、その変転の妙は、見事というほかない。いったい、あれだけの人間があれだけの短時間のうちに、どこへ消えてしまうのだろうか。
 |
|
|---|---|
|
ゴーストタウンと化した街路には時折パトロールの武装ジープや戦車がガタゴトと通り過ぎるのと、パンパンという銃の発射音、そして、夜更けには、ズシンというロケット弾の落ちたくぐもった音も聞こえてくることがある。
ぼくのような、言葉も不自由な一介のツーリストでも、2,3日街をうろついていれば多少は眼が馴れてきて、少しずつ〈戦争〉が見えてくる。
たとえば、列車のターミナル・ステーション。
天井の高い堂々たる駅舎はガランとして、人々の涼み場所になっていた。赤く錆ついたレールは生い繁る草むらの中に消えている。4年前のクーデターをきっかけに内戦が始まったとたんに鉄道が爆破され、以降、列車は止まったままという。
鉄道、道路、橋などを攻撃して交通路の遮断を図るのが戦争の、ゲリラの常套手段。バスも、長距離路線はもちろん郊外路線もストップしたまま。市内循環ルートだけはかろうじて運行中だった。
橋も同様で、街の東に立てば、トンレンサップ川にかかった巨大な橋が中央部で二つ折れになっているのが、いやでも視野に入ってくる。この橋は、シアムレアップやコンポンチャムなど北部の大都市に通じる国道6号線の起点にあたるカンボジア最大の橋チュルイチャンワ橋で、日本の援助で架けられたため〈日本橋〉とも呼ばれているらしい。1972年の8月、クメール・ルージュが中央部の橋桁を爆破。以来、幅500メートルの川をわたるのには襲撃の危険をおかして渡し船に頼るほかなくなった。
プノンペンにはもうひとつ、南の端からスバイリエンを通ってベトナム国境を越えサイゴンまで通じる国道一号線の起点に250メートルほどの橋があり、こちらは〈サイゴン橋〉と呼ばれていた。〈日本橋〉の爆破に懲りて、こっちは軍の守備隊が大勢たむろして警戒していたが、これとても20キロ先はクメール・ルージュの支配下なのだった。
地上・水上の交通路が分断され、政府軍の支配圏はプノンペンやシムレアップなど陸の孤島と化した大都市に押し込められた。したがって、都市と都市を結ぶのは航空路だけとなり、ロンノル政権を支えようとするアメリカは、大量の食糧と武器・弾薬を大空輸しているところだった。
クメール・ルージュの勢力が田園地帯からプノンペン郊外に及んでくると、ロンノル大統領は、近郊農民をプノンペンに強制疎開させた。戦闘地域から避難させるというよりも、ゲリラから切り離す意図が大きいのではないかという人もあったが、いずれにしても首都の人口はふくらみきっていた。食料はアメリカによる空輸で何とか食いつなげるにしても、住宅を建てる余裕がない。少し経済的に余裕のある層はホテル住まいをするわけだが、この状態がこの先いつまで続くか判らない。
当時、政府軍の軍医だったハイン・ニヨルは、1972年ごろのプノンペンについて次のように語っている。
「不思議なことに、この戦争で地方はますます暮らしにくくなるのに、プノンペンではかえって生活が楽なのだ。ひどい目にあっているのは、目を追って増える郊外のスラムに住む難民、将校が軍靴を闇市で売ってしまったので裸足で戦う一般兵士、徴兵にとられた田舎の住民たちで、成金やエリートはパーティを開き、ナイトクラブで遊び、ベンツを乗り回し、召使いを雇って贅沢な生活をしていた。この戦争でプノンペンにかつてないほどの繁栄がもたらされた」(『キリングフィールドからの生還』光文社1990年)
これが1972年ごろ。それから二年後の1974年6月にぼくはこの都市を訪ねたわけだが、ちょうどその頃のことを、ハイン・ニヨルはこう書いている。
「カンボジアのいたるところの町や遠く離れた田舎の村から人々がプノンペンに流れ込んできた。もともと60万人か70万人の人口だったのが、すぐに倍に膨れ上がり、さらに倍増する勢いだった。新しくやってきた人たちはトタン板やダンボール箱や茅で粗末な小屋を作り、物乞いをしたり、不当なほどの低賃金で召使いや労働者として雇われた。だがプノンペンでは、物不足と役人への賄賂のせいで物価がうなぎのぼりに上がってしまった。人々は思いつくかぎりの手を使って金を稼いだ。たとえば、給油トラックの運転手は、ガソリンを配達したあと、タンクの底に少し残ったガソリンをサイフォンで吸い上げてワインの空瓶に移し、それに灯油を混ぜて、路上で売った。ガソリンより値段は安いが、エンジンには悪いしろものだった。
(後編へつづく)
(1992年 南船北馬 NO.13 掲載) |