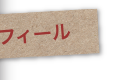■ 救護物資の行方
神戸市灘区も、JR六甲道駅一帯を始めに甚大な被害を被った地域である。軒並み家屋が倒壊し、火も出た(灘区全体では1万2千188軒が倒壊、3万5千人が避難所生活をした、とされている)。
六甲山の山腹の傾斜にある神戸大学国際文化学部の体育館にも千人を越える人たちが避難していた。私の義弟一家も親子4人でここに身を寄せていた。ここは、甚大な被害を受けた住宅地からはかなり離れた場所であり隔絶された感じもあったが、彼らは一瞬にして倒壊した家屋の下で生埋めになり着のみ着のままで救出された時には、近くの成徳小学校や鷹匠中学校などはすでに避難者であふれており、さまよった末にこの坂の上の避難所にたどりついたのだった。ここでも4人家族に与えられたスペースは布団2枚分がせいいっぱいだった。敷き布団1枚、掛け布団1枚、毛布4枚。これが一家4人分の〝寝具〟だった。
何度か見舞いに訪れていたにもかかわらず、私がそのことに気づいたのは2月も半ばになってからだった。彼らは体育館のフロアに直接布団を敷き、もう1枚分のスペースには毛布を敷いただけで、冷え込みのきつい夜を過ごしていたのだった。館内は、火の用心のために火気厳禁。電気容量も少ないために電器製品も使えない。
西宮市内の避難所には、市が手配してウレタンマットや畳などの断熱材が敷きつめられたというのに、ここにはいまだに何の下敷きもないのか……これまで何度も訪れながら、私はそのことに気づきもしなかった、そのうかつさにがく然とする思いだった。出入りのボランティアたちも気づかないのだろうか。直後の、どさくさ期にはともかく、1ヶ月もたってしまうとその状態が常態と化してしまい、断熱材が敷かれていることなど当然のこととして、確認することすら思いつかなかったのである。
当事者たちも、冷える冷えるといいながら、それも含めた不便不自由辛苦の生活を被災・非日常体験として受け容れ、忍ぼうとしている気配だった。「国立大学」の施設に〝居候〟していることへの遠慮もあったようだ。
自治体の行政当局やボランティアに対しても、水と食料、避難場所という一次的絶対的生活必需物資の提供、さらに布団・毛布・衣類など二次的救援物資の提供を受けているだけに、そのうえ断熱材という〝副次的〟なものの要求には、ためらいがあったのかもしれない(ぜいたくは言えないという自制)。
それでも、避難所には高齢者も多く底冷えがこたえるので、避難所生活者の自治組織の「世話人会」は、せめてこのような人たちの分だけでも何とかならないだろうかと、神戸市の災害対策本部に対して断熱材配給の要請は出していたという。
「分かりました。なんとかします」というのが、その返事だった。だから彼らは待っていたのだったが、1ヶ月たっても、なんともなっていないのだった。なにしろ大変な時なのだから仕方がないと彼らは黙って耐えているのだった。
そのことに、私たちは、もっと早く気づくべきだった。
神戸市の災害対策本部もマニュアルのない膨大な仕事に忙殺されているにちがいない。ここは、余裕がないのである。
それなら他のルートに当たってみるという手もあるのだが、市が「なんとかする」と言ってくれているのに、他に頼むというわけにもいかないだろうと彼らは言う。
では、私たちのような〝外部の〟者が勝手に動くのならかまわないだろう。震災直後に朝日新聞大阪厚生文化事業団が神戸の灘区に設置した「朝日ボランティア基地」を運営している友人に電話して事情を説明すると、打てば響くような応答をしてくれた。
「避難所に敷く断熱材を千人分なんとか都合つかんやろか」
「わかった。確認するから10分後に電話してくれ」
10分後。
「自衛隊が畳を千枚持ってるそうや。今なら便があるから、避難所まで運んでくれると言ってるけど、どうする?」
私は喜んで避難所にそのことを伝え、受け容れできるかを確認すると、意外なことに、答は「ノー」だった。畳の話はいままでにもあったのだが、世話人会の方で辞退したのだという。
いったいどういうことなのか。
どうやら、大学当局から、畳を敷くのは遠慮するよう釘をさされているらしい。その理由は、体育館の床に傷がつくからというアホらしいものらしかった。
あまりにもアホらしく、にわかに信じ難かったので、その真偽の程を質そうと、神戸大学国際文化学部の事務室に電話してみた。電話の相手が何人か変った末に、結局「大学として、そのようなことを申し上げたことは一切ございません」というのが回答だった。
「でも、避難所の者には、大学の事務長さんがそう言われたと思っている人もいるんですけど、それは何かの間違いなんでしょうかね」
「いずれにしましてもね、避難所の方々が会議を開いて自主的にお決めになったことですから……。わたしどもとしましては皆さんに対してああしろこうしろと申し上げる立場にはございませんので……」
「では、避難所の世話人会で畳の受け容れを決めれば、大学としては差し止める理由はないのですね」
「避難所のみなさんが、そうお決めになるのでしたら……」
さっそくそのやりとりを避難所に伝えたものの、やはり世話人会は畳を辞退するという方針を変えなかった。大学の表向きの公式見解よりも、その背後にある本音に従おうとする〝居候の仁義〟を優先したらしい。この避難所に限らず、巷には、居心地をよくするといつまでも避難所を出ていこうとしないので施設管理者たちは畳を敷くのを嫌がるのだ――との憶測が、かなりの説得力をもって流れていたのも事実だった。
一方には、こんな事態なのにそこまで遠慮することはないだろうに、という思いはあった。現に、「被災者」という立場を全面に出して〝何でもあり〟〝やったもん勝ち〟〝問答無用〟の現実もあちこちに見られ、ひんしゅくをかう者もいた。ここの世話人会は、できるだけそのようなゴリ押しは避けるつもりらしかったので、私たちはその美学を尊重したいと思った。
彼らの意向をふたたび朝日ボランティア基地に伝え、床を傷つけないウレタンフォームや発泡スチロールの断熱材を探してもらえないだろうかと相談をもちかけた。畳の件を検討しているあいだに次の策を探っていてくれたらしく、彼はすぐに情報をくれた。
「三木市にある兵庫県三木山森林公園の中に、県が管理する援助物資の貯蔵所があるのだが、うちのスタッフのひとりがそこで断熱マットを見たと言っている。いっぺん電話してみ。電話番号は△△。現場の責任者は○○さん。そこがだめならまた次を考えることにして……」
さっそく教えられた番号に電話してみた。
「ええ、畳1枚分ほどのサイズのものがあるはずですよ。私の背丈の2倍くらいの高さに積み上げた山が2つあるのは確かです。何枚あるかはわかりません。一度見にきてもらえませんか」
「それを、もらって帰ってもよろしいか?」
「いいですよ」
三木市は神戸市の北西部に隣接している。神戸市内を通過できない車の迂回路のひとつにもなっていて、トラックで大渋滞の道を三木山森林公園にたどりつくと、園内には博覧会のパビリオンのような色とりどりのテントが立ち並んでいて、それが物資の貯蔵倉庫がわりなのだった。現場のボランティアスタッフに事情を話すと、巨大なテントのひとつに案内してくれた。その一隅に、断熱マットの予想以上に大きな山があった。材質やサイズや厚みの異るマットの梱包を積み上げた山が、ひとつふたつみっつ……5つ以上あった。目分量で、ざっと千枚。胸がふるえる。
「これぜんぶ欲しいけど、よろしいか?」
「どうぞ。でも、どうやって運びますか?」
「確保しといてください。あしたトラックで引き取りに来ますから」
あったあった、千枚の断熱マットがあった。興奮を隠しながら、見本を10枚ばかり車に押し込んで避難所に届けると、今度は世話人会は受け入れを決めた。
それにしても、神戸市の災害対策本部は兵庫県の災害対策本部のデポの中のマットを発見できなかったのだろうか。あるいは、わずか千枚しかないシートを特定のひとつの避難所だけに支給することで〝公平〟を欠くことをはばかったのだろうか。全てに公平に分配できない半端な数の物資は、死蔵されても仕方ないと思ったのだろうか。それとも、たんに探さなかっただけなのか。断熱マットや間仕切りのついたてを支給した西宮市の避難所人口はピーク時でも〝わずか〟4万5千人だったのに、神戸市のそれは24万人にものぼったわけで、とてもそこまで手がまわらなかったという事情は理解できる。
しかし、余裕のなさゆえに直接手当ができないなら、そのことを市民に伝えるべきだろう。あなた方の判断と力量で何とかしてくださいと伝えるべきだ。だのに、「わかりました、なんとかしましょう」などと応えるのは、それが当面の「○」だからだろう。
いずれにしても、このたびの震災では、実に32万人もの人々が避難所に身を寄せるという未曾有の事態が出現したのである。しかもこの数字は「被害救助法に基いて」運営された 〝公的〟な避難所への避難者の数を各自治体が集計したものであって、それ以外の場所、たとえば個人の家など〝私的〟な場所に避難・疎開した人の数は含まれていない。
これら一朝にしてほとんど無秩序に出現した避難所に膨大な数の人びとが押し寄せたにもかかわらず、しかも「法に基く運営」の実態がちぐはぐで混乱の見本市の様相を呈していたにもかかわらず、〝高見の見物者〟たちが懸念したような大規模なパニックに陥ることがなかったのは、やはり驚異というべきだろう。古来あまたの地震・干ばつ・風水害など天災に遭遇してきたこの島国の住人が文化として共有する自然の猛威への畏怖、天災への諦観といった心性が、このたびの突発的な大災害に際しても呼び醒まされたのだろうか。
そう考えれば、「法に基く避難所」の運営を巡って繰り返された茶番劇も、当事者のリアルな日常を活性化させる狂言まわしの役割を果たしたと言えるかもしれない。
(大震災・市民篇 1996年 長征社)