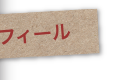砲撃中の大砲のかたわらですやすや昼寝する赤ん坊 M16ライフルをおもちゃにして遊ぶ子どもたち 機銃掃射をあびながら笑いころげる兵士たち ポルポト派の攻撃によって陥落寸前のプノンペンと その郊外の前線で見聞きした〝不思議な戦争〟 |
 |
|
|---|---|
|
ハイン・ニヨルは、続けてこう書いている。
「四六時中、そんなガソリン売りが路上で瓶を振って買い手を探していた。教師はタクシーの運転手になり、病院の医師や看護婦や用務員は仕事をサボって、別の診療所で働いたり、薬局から盗み出した医薬品を売った。軍の将校は“幽霊兵”(兵士の数を水増ししその分の給料をネコババしているため)の代わりとなる本物の兵士が必要になると、夜にトラック部隊を出して映画館の外で待機させた。映画がはねて出てきた若者は、賄賂の金を持っていないと、トラックに積み込まれて連れ去られた」(『キリングフィールドからの生還』光文社1990年)
この街に来ていちばん往生したのは、地図が手に入らなかったことだった。カンボジア全土のもプノンペン市街のも、手に入らなかった。空港でもホテルでもツーリストビューローでも、「地図はない」という返事ばかりだった。本屋にも、なかった。
ぼくの言葉が通じないせいなのかとも思って、英語の通じるカンボジア航空のオフィスにも行ってみたが、やはり、なかった。
応待に出た女性は、とびきりの美人だった。
「残念ながらここにはありませんが、観光省にはあるかも知れませんよ」
彼女はとろけそうな笑みと声で道順を教えてくれた。
メモをたよりに歩いてみて、驚いた。“官庁街”は、バリケードと番兵だらけだった。道路は寸断され要所要所に鉄条網が張りめぐらされ検問所が設けられていた。建物のほとんどは窓がかくれる高さまで周囲に土嚢を積み上げて市街戦に備えてあった。狭めた出入口には見張り小屋があり、機関銃座から武装した兵士がにらんでいる。コンクリやレンガの塀に囲まれている場合は、内から応戦するために所どころ穴をうがって銃眼がこしらえてある。
ようやくたずねあてた観光省とおぼしき役所は、きれいさっぱりと“開店休業”の様子。かつては、偉大な仏跡アンコールワットを訪れる大勢の観光客を受け入れていたのが嘘のように、ガランとしている。それでも出勤している人は何人もいて、するべき仕事のないまま、デスクでお茶を飲んだりタバコをふかしたり談笑したりして時間をつぶしているらしい。
いちばん奥で偉そうにふんぞりかえっている人物にきいてみた。
「プノンペンの市街地図があったらもらいたいのですが」
「あなた外国人?」
「日本人です」
「われわれは、政変以降プノンペンの新しい地図をつくっていません。だから、あなたにあげる地図はありません」
「なら、古いので結構。十分です」
「古いのは通りの名前がホーチミン通りとか毛沢東通りとかなっているので、あげるわけにはいきません。いまはすっかり変っていますので。アイムソーリィ」
「どこに行けば手に入るでしょうか」
「知りません」
とりつく島がない。
しかし、ぼくは意地になっていた。ほんとうに地図はないのだろうか。それとも、ぼくが外国人だから〝防衛上の理由〟から、ないと言っているだけなのだろうか。
そこで、ふと思いついた。外国人だからダメだというのなら……日本大使館に行ってみようか、地図がなくて困っている日本人に何か情報をくれるかも知れぬ――。そうひとり決めして、観光省の役人に場所をたずねたら意外にも親切に教えてくれた。
探し当てた日本大使館も、この国の役所と同様、市街戦にそなえた構えだった。日の丸を掲げた建物を囲む塀の数カ所に銃眼用に穴をあけてあるし、窓には前に土嚢をうず高く積み上げて塞いである。玄関脇には開襟シャツのクメール人たちが軽機関銃を抱えてたむろしている。
一階のオフィスに日本人らしい顔はなかった。
「プノンペンの地図はありませんか?」
「ありません」
「どこに行けば手に入るでしょう」
「知りません」
ここでも、とりつく島がなく、手ぶらでそこを出た。日本人の大使館員は、どこにいるのだろうか。
地図のないまま街をうろついて3日たった。4日目の朝、例によって雑踏の中をぶらついていると、背後で声がした。
「マツミヤサン……」
誰かがぼくの名前を呼んでいる。でも、まさか。クメール人の会話の中に偶然似通った発音があっただけにちがいない。
「マツミヤサン?」
今度は、はっきりぼくの名前が呼ばれている。いったい誰が? いぶかりながら振り返ってみたが、知った顔はない。
「やっぱりマツミヤサンでしたか」
はっきりした日本語だ。
人込みの中から丸顔の小柄な初老の男が近づいてきて、ぼくの腕にふれた。
何事が起こったのか、事態がとっさには呑み込めず緊張でからだがこわばったまま、その人物の顔をまじまじと見つめることしか、ぼくにはできなかった。ひょっとしたら闇ドルの売買がバレたか、あるいは、しつこく地図を探し歩いていることでスパイか何かに間違われたか? いずれにしても官憲方面からの接触と直感した。
「わたし大使館の者です。あなたを探していました」
そのとき、とっさにぼくは「彼」のことを思い浮かべた。
ぼくが泊まっているインターナショナルホテルの二階のロビーのソファに三人組の若い女性がいつもたむろしているのだが、彼女たちはベトナム人で、この街に「出稼ぎ」に来ているらしかった。彼女たちを毎日訪ねてくる青年がいて、彼は英語を話すのでぼくも親しくなった。グエン・チャン・タンというベトナム人で、南ベトナム大使館員だという。仕事は何かと問うと、「ミリタリー・ポリス」だという。
はて、ミリタリー・ポリスといえば、「憲兵」のことか? 見たところ彼はとても憲兵に見えないが……それにしてもベトナムの憲兵がこんなところで何をしているのだろうか――。ぼくが浮かぬ顔をしていたと見えて、「ほら、これ見てよ」と言いながら、IDカードを取り出した。見ると顔写真の下に「Secret Service」の文字があった。
おいおい、シークレット・サービスかよ、いったいこんなもの他人に気軽に見せて大丈夫なのかねえ。シークレットなんだろ?――というようなことを言うと、
「ノープロブレム」
彼は涼しい顔でそう答えたが、やはり、情報収集が彼の任務なのだろうか。しかし、どう見てもジェームズ・ボンドのような仕事ではなさそうだった。三人の女の子たちは、彼の配下で、「客」を通じて情報をとっているのだろうか――はっきりしたことは何もわからないまま、気になっていたものだから、「大使館の者です」と聞いたとき、とっさに彼を思い出したというわけだ。
「大使館? どこの大使館ですか?」
「日本大使館です」
「いったい、ぼくに何の用ですか?」
「そこらの茶店に寄りませんか、そこでお話しましょう」
近くの屋台に腰をおろし、〈おかゆ〉でもいかがと言うので、それと豚足の煮込みをつつきながら話を聞いた。話は次のようなものだった。
「この国の状況はご存知のように風前の灯です。日本大使館は、この国に滞在する日本人の生命・財産の保護が困難になってきたため、国外へ退去していただくよう勧告を出しています。大使館の関係者とジャーナリストを除いて、ほとんどの日本人は国外に出ました。従ってあなたにも退去していただきたいと、そのことをお伝えするために、あなたを探していたのです」
「ぼくが入国したことがどうして分かったのですか?」
「先日、空港のイミグレーションから、あなたが入国なさったと報告がありました。入国カードには、あなたの滞在先がホテル・ル・プノンとなっていましたのですぐ電話しましたが、そのような人は泊まっておられないということでした。その後も出国なさった様子がないので街の中を探していたところ、こうして見つけたというわけです。一応、勧告はお伝えしましたが、もしよろしければ大使館まで同道ねがえませんでしょうか?」
ぼくは、断った。
もし、そういう勧告が出ているのなら、きのう大使館へ出向いたとき、なぜ伝えてくれなかったのか――。
「あなたとおぼしき人が来られたことは存じていますが、応待した職員は、あなたを日本人と思わなかったようです。だから、その時お伝えできませんでした」
どちらにせよ、ぼくは、大使館には出頭しない、この国からも出ていかない――という意思を伝えた。
「しかしそれでは、職務上あなたが困るでしょうし、申訳ないので、必要なら一礼入れますよ。勧告は確かに承知したこと、その勧告には従わず自らの意思で滞在すること、したがって、もし私の生命財産に万一のことがあってもその一切の責任は私自身にあること――以上のことを文書にするので大使館にもって帰ってください」
そして、次のような意味のことをつけ加えて話した。
「ぼくがこの国に来た動機や目的はまったく個人的なものです。戦火にさらされたこの国の普通の人々の日常生活を知りたいということです。ジャーナリストとして取材に来たのではなく、ぼく自身の問題として〝感じる〟ために来たということです。まったく独善的で勝手な言い分だと自分でも思います。だから、大使館の保護を受けられなくても文句はありません。もっとも、ぼくもまだ命は惜しいので、せいぜいおとなしくしているつもりではありますが……」
こんな手前勝手な口をきくガキは、人(大使館)の迷惑を考えない不逞の輩と思われても、仕方あるまい。
だのに、その人は、ぼくの返事を納得してくれただけでなく、「日本人の若者の一人として、しっかりこの国のことを見ていってください」と、反対にはげましてくれた。この反応には、ぼくの方が驚いた。
ぼくの日本での本籍地、現住所、パスポート番号などをメモしたあと、フリーランスのレポーターとでも報告しとこうか?と笑いながら言うので、思わず、「あなた、日本人ですか?」と訊いてしまった。こんな反応や発想をする人は、大使館員には珍しいと思ったからだ。
直感通り、この人は日本人ではなかった。現地採用のスタッフで、カンボジア国籍の台湾人だとのことだった。日本名も持っていてコマイ・イエヨシ(駒井家義)というのがその名前だそうだ。第二次世界大戦の末期、大日本帝国の植民地だった台湾から陸軍の兵隊として仏領インドシナに送られてきたのだが、日本の敗戦後、置き去りにされたという。以後、無国籍者としてずいぶん苦労なさったらしい。この地方にも、いわゆる〝華僑〟の人たちは強く深く根を張っており、この国の経済活動の中枢をになう存在になっているわけだが、その人たちの多くは中国系といっても潮州出身者が大部分で、台湾出身のコマイさんは言葉も通じず融け込むのは難しかった。
苦労の末、やがてクメール人の女性と結婚したことでカンボジア国籍を得ることができたし、日本語が堪能なので日本大使館に職を得ることができた。
そして、この戦争。いよいよプノンペンも敗色が濃くなった現在、妻子はパリに疎開させてあるという。
ぼくは、コマイさんの生いたちを聞いて、言葉がなかった。彼の、日本および日本人に対する思いはきっと複雑に交錯しているにちがいない。
ぼくの泊まっているホテルの一晩の泊り賃が3ドル50であることを知ってコマイさんは、街の中心部にあるホテルに移るようすすめてくれた。そこなら一晩1ドルで済むし、中央市場のそばだから安全だよ、と彼は言う。つまり、その一帯は人口密集地だから庶民の暮らしがよく見えるし、クメール・ルージュが夜闇にまぎれて撃ち込んでくるロケット弾の目標にもなりにくいはずだとの判断があってのことらしかった。
紹介されたのは「ホテル・アジア」。一晩800リエルだった。「ドル払いでなくていいよ」。帳場のマダムは太太の貫禄を見せて鷹揚に言ってくれた。街で新しく見つけた闇ドル屋のレートがちょうど1ドル=800リエルだったこともあって、さっそくこっちへ引っ越してきた。
ホテルは、中央市場から100メートルと離れていない文字通りプノンペンのド真中、にぎやかで活気にあふれた棟続きの商店街の階上にあった。場所柄のせいもあってか、えたいの知れぬ人物を含む雑多な住人たちと、以後幾晩もの長い夜を共にすることとなった。
引っ越した日の午後、コマイさんはぼくの様子を見に立ち寄ってくれ、外出禁止時刻が迫るまで話し込んでいったが、おかげで戦闘の状況や街のアウトラインについて詳しいレクチャーを受けることができた。
「ところで、前線には行ってきましたか?」
「いえいえとんでもない。言葉ができないうえに、地図も手に入らないので、ただ街をあてもなくうろつきまわるだけですよ。ホテルにカン詰めになっても仕方がないと覚悟してきましたから……。このホテルなら、あと1ヶ月この調子で暮らせそうです」
「でも、せっかくプノンペンに来たのですから、前線を見ていってください。おそらくこの戦争のありさまが、もっとよく見えるはずですよ」
「いけるものなら、ぼくも前線に出てみたいけど、ツーリストの身分では無理でしょう」
「この国の現政府はすでにそこまでコンロトールする力は持っていません。崩壊は時間の問題でしょう。傀儡政権の末期の表情を日本の青年にしっかりと見ておいてもらいたいと思います」
「プレスカード(取材許可証)もなしに前線に出て大丈夫でしょうか」
「プレスカードがあれば大丈夫というものでもないですよ。政府軍の士気はすっかり衰えているし、敵も、きついようだしね」
コマイさんはそう言いながら、カンボジアの戦争を取材に来て死亡あるいは行方不明になった日本人ジャーナリストの名前を、教えてくれた。
●フジテレビの高木と日下が国道1号線のスバイリエンで。
●日本電波ニュースの柳沢と百合野が2号線のカンポットで。
●CBSの石井と坂井、NBCの和久が3号線のカンソポットで。
●東京オブザーバーの中島は、3号線のどこかで。
●UPIの沢田は2号線の34キロ地点で。
●共同通信の石山は5号線の50キロ地点、サラレックプラムで。
●フリーカメラマンの一ノ瀬は6号線のシェムリアップ付近で。
合計11人の日本人プレスマンが、この戦争が始まった1970年から73年までのわずか3年のあいだに死亡するか行方不明になった。もっと長期かつ大規模な戦闘の続くベトナムで死んだ日本人ジャーナリストが3人であったことと比べると、その人数の大きさがわかるだろう。これらの人の名と所属と場所を、コマイさんは克明に記憶し、そらんじているのだった。
「去年(1973年)の10月に石山さん、11月に一ノ瀬さんが相次いで行方不明になりました。どこかで生きていてくれればいいのですが……」
その後、数年たって、この人たちの遺稿集や追悼の本が何点か出版された。そのうち、ぼくは、中島照男、沢田教一、一ノ瀬泰造に関する本を何冊か読む機会があった。年齢はそれぞれ、中島27歳、沢田34歳、一ノ瀬26歳。一ノ瀬はぼくと同い齢だった。彼が、クメール・ルージュの支配下にあるアンコールワットの写真を撮りに出かけたまま消息を絶ったのは、ぼくがプノンペンを訪れるわずか7ヶ月前のことだった。「地雷を踏んだらサヨウナラ」との言葉を残して。(『一ノ瀬泰造写真・書簡集/地雷を踏んだらサヨウナラ』講談社1978年)
ホテルを移った翌日、コマイさんのレクチャーを思い出して、とにかく前線に近づいてみることにした。コマイさんの判断では、国道1号線と5号線がいいだろうとのことだった。プノンペンからほぼ放射状に6本の国道(1号線~6号線)が延びているが、そのうち、1号線はベトナム国境を越えてサイゴンに至り、五号線はタイ国境を越えてバンコクに達する幹線道路である。
まずは1号線に出かけてみることにした。サイゴンまで230キロメートル、ベトナム国境までならわずか160キロメートルである。
ホテルの近くの中央市場からトヨタの軽トラックを改造した乗り合いバスで市街の南の端まで走ると、そこにかかる「サイゴン橋」のたもとが終点だった。300メートルほどの橋を歩いてわたると検問所があった。ここでは、橋をわたってプノンペンに入ろうとする自動車のチェックが行われていた。テロや破壊工作に使われる爆発物を探しているようだ。
そのわきにある茶店の床几に腰かけてコーヒーを飲みながら、しばらく見物を決めこむ。
ボンネットやトランクを開けて中を調べたあと、棒の先に鏡をつけた道具で車の腹の下をのぞき込むという手順のようだったが、調べる方にも調べられる方にも、どちらかというと、のんびりした雰囲気がただよっていた。
検問にあたる兵士たちは、上半身裸。橋をわたる自動車は少ないので日陰のベンチでお茶を飲みタバコを吸いながら、ぼんやりと道を眺めている。車がやってくると、やおら数人が立ち上がって作業を始めるのだが、どこかおざなりで緊迫感はまるで感じられない。ひと仕事終えるたびに彼らはまた日陰に帰ってお茶とタバコをやりながら談笑をはじめる――ということを繰り返している。
そうするうちに、首都側から1台のメルセデスが橋をわたって来るのが見えた。フロントガラスに大きな貼り紙があって、「PRESS/REUTER」と書いてある。その下にあるクメール文字もたぶん同じ意味の言葉なのだろう。
ロイターの特派員の車らしい。車が止まると、1人の白人の巨漢が降り立った。半ズボンにポロシャツ、サンダル。首からカメラをぶら下げている。一見すると避暑地の観光客風だ。続いて降りてきたのは、ホットパンツにノースリーブ、サンダルにサングラスという、これもリゾート客風のギャルが三人。中国系かクメール系か判然としないが、いずれもカンボジア人らしい。にぎやかにはしゃいでいるので、あたりが、ぱあっと華やいで見える。
白人の大男は、つかつかと検問所の小屋に入って何やら話を始めた――と、見ているうちに、ここの責任者らしい兵隊が出てきて声を挙げた。
半裸でくつろいでいた兵士はノロノロと立ちあがり、上着をつけ、肩から腰にかけてのベルトをつけ、ヘルメットをかぶり……たぶん本来の警備兵のかっこうなのだろうと思われる服装と装備を整えて全員が集合。ちょうど通りかかった車を止めて、いつもの作業にとりかかった。
今度は、車に乗っている人を全員降ろして座席の下までのぞき込んでいる。そのそばには、ライフルを腰だめに構えた兵士が立ち、責任者らしい人物が指揮して作業が進んでいく。
おいおい、さっきまではそんなやり方してなかったじゃないか。
その様子を、半ズボンの白人がパシャパシャと撮影し続けている。時々、注文をつけると、兵士たちは動きを止めて、はい、ポーズ。
「首都への入口で車の検問をする政府軍の兵士たち」――と、キャプションをつけるに相応しい構図が出来上がったというわけだ。
わきの方ではしゃいでいるピンクや黄色のホットパンツ・ギャルたちの姿は、もちろんファインダーには入らない。
ひとしきりシャッターを押しまくったら、オーケー、サンキュー、という調子で手を振りながらメルセデスはプノンペンに向けて橋を戻っていった。あと何時間かしたら、ロイターの契約先にプノンペン発のこの写真が配信されるのだろうか。
メルセデスが去ったあと、汗みずくの兵士たちは、やれやれといった表情でヘルメットをとり上着を脱ぎながら、緑陰に戻ってくるのだった。
ぼくが目撃したこの取材風景は、ことさらめいて「やらせ」などと言うほどのことではないルーティーンワークなのだろう。しかしながら……とぼくは考えた。首都への入口で検問する兵士たち―という事実に違いはないにしても、その兵士たちが〝正装〟して仕事をしているのと、半裸でチンタラしているのとでは、おのずと写真の持つ意味が違ってくるはずだ。プノンペンの「犬」についての記事もまた、同様のレトリックと言えよう。
検問所の隣にある屋台でお茶を飲みながら高見の見物を決めこんでいると、同じテーブルにいた若い男が声をかけてきた。
「この1号線の先の方に行く気ありませんか? わたし案内しますよ」
英語だった。
できるだけ目立たないよう地元の市民にとけ込むよう服装にも気を配っていたつもりだが、
“戦争を取材に来た外国人”の1人として見当をつけられていたらしい。
年格好は、ぼくより年下の感じ。クメール人だろう。顔の表情や話しぶりからすると、ちょっと胡散臭い。しかも、いきなり戦場ガイドの売り込みとくれば、こっちも警戒せざるを得ない。
「戦闘はあると思うか?」
「もちろん。でも心配ないよ、オレがバッチリ案内するから……」
こんな風に声をかけて来る奴は、だいだい調子がいい。こっちの態度に警戒の色を見てとった彼は、ズボンの尻ポケットからパスを取り出し、中からカードを抜いて、ぼくに見せた。IDカードだった。
それによると、彼の身分は「アメリカ合衆国大使館の運転手」だった。(ああ、また大使館!)顔写真も本人のものだった。非番の日に“戦場ガイド”のアルバイトをしているらしい。
どうだ分かったか、怪しい者ではないだろう――彼はいかにもそう言いたげな表情でぼくを見つめているが、ぼくとしては、この3日のうちに、ベトナム・日本・アメリカとたてつづけに大使館関係者とかかわることになったわけで、何やらおかしくなって、つい苦笑してしまった。
「オーケー、決まった。さっそく出かけようぜ」
ぼくの苦笑を承諾のサインと勝手に了解して彼は握手を求めてくる。
「チョト待テ、ねだんイクラ?」
主導権をとられてぼくはあせった。だが事前に料金の交渉をしておくという原則をかろうじて思い出した。
五千リエルと言うのを値切ったら3000リエルにしてくれたので「じゃあ、ひとつ行ってみるか」ということになった。3000リエルは闇レートで約4ドルほどになる。
乗り物は自動車ではなく、ハーレーダビッドソンの大きなバイクだった。後ろのシュートにまたがったとたんに、ビュンビュンと風を切って走りだした。ほんまに大丈夫やろか? ちらと不安が頭を過ったものの、もうその時は何キロも走ったあとだった。
「ほら、あれを見て」
まっすぐの道を突っ走りながら、エンジンと風の音に負けないよう大声でどなりながら彼が指差したのは、銃弾でハチの巣になった広告板だった。2メートル×4メートルほどの鉄板に字と絵が描いてある。ペンキがはげて弾痕の周囲は赤錆におおわれている。国道沿いに次々と現れる看板はことごとく何十何百という銃弾が浴びせかけられて穴だらけになっていた。
国道1号線はメコン河に沿って東に延びている。いまにも降り出しそうな厚い雲。遠雷の響きが聞こえてくる。バイクはおかまいなしに突っ走る。ぼくは、ふり落とされないよう必死でしがみつく。
走るうちに、雷鳴が近づいてきた。――と思ううちに、道路とメコン河の間に広がる森のむこうで、いきなりドカンときた。
落雷か? あれは何の音だ、ぼくはドライバーの肩をたたいて耳元に叫ぶ。彼はエンジンの音に負けじと怒鳴り返す。
「ガン!」
ガンと言われても、何のことか分からない。
「ガンて、何?」
また背中を叩いて問い直す。
それがどうやら大砲の射撃音らしいと分かるまで、だいぶん時間がかかったが、知らぬ間にぼくらのバイクは戦闘地域の中に入り込んでいたらしい。先ほどから聞こえていた雷鳴は、あれはどうやら砲声だったようだ。部隊は、森のむこうでメコン河畔に展開しているらしい。
それでも、バイクは突っ走る。
突然、カタカタカタ……パラパラパラ……乾いた音が風に乗って聞こえてきた。
「あの音はなんだ」。思いっきり肩を叩いたら、「マシーンガン!」との返事。
「マシンガン? 機関銃? おいおい、大丈夫かいな、危ないよ」
「オー、ノープロブレム」
ハーレーは、いっこうに止まる気配がない。
ホテルで寝ているときも、そう言えば、同じような破裂音が夜の街にこだましていたのを思い出した。
外出禁止令によって宵のうちから閉じこめられた人たちが、うさ晴らしに爆竹を鳴らしているのかと思っていたのだが、さては、あれは銃声であったのかと、このとき突然、思い至った。
機関銃にせよ小銃にせよ、〝銃声〟はぼくたちの暮らしからは縁遠いものだった。“銃声”といえば、映画や劇画やテレビドラマで表現されるものだった。それらのメディアを通じて“知っている”銃声は、どちらかといえば荒々しく兇々しく圧倒的なものというイメージだったような気がする。文字にすれば、ダーン、ドキューン、ダダダダダッ……という具合に。実際、劇画では大きな文字でそう表現されている。
だのに、いまこうして耳にしている音は、あっけらかんとしてリズミカル。南国の田園を風に乗ってわたってくる〝のどかな〟音。ここが戦闘地域であることを知らなければ、これが銃声とは、とても信じられないほどだ。
このズレは、いったいどうしたことか。
メディアを通じてぼくの“知っていた”射撃音は“擬音”であり“効果音”であり、いわば演出・加工された“イメージ”だったのだ。
そして一方に、熱帯の平原を流れる“母なるメコン”のほとり、悠久の流れ=平和な風景――というイメージ。
これら相反するイメージの間の大きなギャップ。二つの異質なステレオタイプのはざまで、ぼくは混乱したらしい。
混乱したままバイクにしがみついていると、左前方の田んぼの中に、とうとう大砲が見えだした。本当にドカンドカンとやっている。その囲りでは塹壕を掘っている。
なんだ、これは。こんなところをバイクにまたがって走ってていいのだろうか――。いかにも
“観戦ツアー”のようで気がひける。不謹慎なふるまいと見えはしまいかと、うしろめたい。そればかりか、戦闘のとばっちりを受けたら我が身も危ない――。ぼくは、たちまち怖気づいて、街に帰りたくなった。とにかく引き返さねば。
「オーケー、もう十分だ、引き返そう。聞こえたか? プノンペンに帰ってくれ」
ドライバー君の肩をたたいて必死に大声を張りあげるのだが、彼は、ノープロブレム、心配するなと叫び返して、走り続ける。
これはエライことになった。ぼくは恐怖にかられて、生きた心地がしなくなっていた。
結局、バイクはコキという小さな町に入って、ようやく止まった。プノンペンから1号線を走って最初の町――というより街道沿いの宿場といった感じの集落だったが、露店には大勢の人がたむろしていた。
何よりも驚いたのは、10歳前後と思われる少年たちが手に手にライフルをもって歩きまわっていることだった。そのライフルは、あのゴルゴ13が使っているのと同じ型のようだった。訊ねると、M16と呼ばれる米軍の正規(制式モデル)銃だという。首都防衛隊に志願すると、たっぷりの弾薬といっしょに支給されるらしい。
この集落は、1号線方面の首都防衛前線基地になっているようで、兵隊の姿も多い。もちろん、少年たちは兵隊ではなく、ボランティアだ。でも、米軍用の兵器・弾薬・装備・衣服・食糧などがふんだんに供給されるので、年ごろの子は喜んでこの〝仕事〟に就くのだと、ガイドが説明してくれた。ブカブカのヘルメットに野戦服、M16をはじめとするいろんな銃器、弾帯を袈裟がけにした上に手榴弾まで腰にぶらさげて、彼らは闊歩しているのだった。大口径のグレネードランチャー(擲弾銃)を弄んでいる子どももいる。
しかし、ぼくの目には、まるで「戦争ごっこ」で遊んでいるようにしか見えなかった。本物の戦争ごっこ――。
プノンペンからここまで、東行するメコンの右岸に沿って19キロメートル。ここから先は、〝解放軍〟の支配下にあるらしい。
屋台でお茶を飲みながら、ガイド君はレクチャーしてくれる。そして、この道のもう少し先では銃撃戦をやっているはずだから、そこまで行ってみようと、恐ろしいことを言う。
いったい彼らはどういう神経をしているのだろうか、わずか数キロ先に〝敵〟がいるというのに、まったく緊張感というものが感じられない、それどころか、こうしてのんびりと昼下がりのお茶を〝楽しんで〟いる――かのように、ぼくには見える。〝戦争〟に関するぼくのステレオタイプとの、このギャップ。
ぼくはと言えば、ドカンドカンと発砲する大砲を目にし、機関銃の発射音が聞こえてくる町の中で、ライフルをかかえたミリタリールックの男たちに囲まれているだけで、怖気づき恐怖にかられて地に足がつかない。
ガイド君はのん気なことを言っているが、ぼくはもう1キロも進みたくなかった。プノンペンに連れて帰ってくれと繰り返すうちにようやく彼も引き返す気になった。
再びハーレーダビットソンにまたがって国道1号線を引き返しはじめたら、スコールが来た。文字通りバケツをひっくり返したような勢いで雨が降る。このスコールを突っ切って、ぼくたちはホテルに帰り着いた。
この日の出来事は、思いがけないきっかけからの成りゆきだっただけに、強いインパクトをぼくに与えたのだった。いきなり、実戦中の大砲の横をバイクで走り抜けるという体験は、めったなことではないだろう。
その夜、ぼくは、いつまでも寝つけなかった。遠雷のように、夜半聞こえてくる砲声が、この夜はずいぶん違って聞こえてくる。ぼくはいつまでもその音をきいていた。
「よし、あしたは5号線を行ってみるか」
ぼくは、馴れてきたせいか次第に〝その気〟になっていた。
 |
|
|---|---|
|
5号線は、プノンペンからトンレサップ川に沿って北上してトンレ湖に至り、そこから北西に向きを変えバッタンバンを通ってタイとの国境を越え、バンコクまで通じる幹線である。10ヶ月後にプノンペンが陥落し、ポルポト政権による〝大量殺戮〟が行われた際、キリングフィールドから逃れ出たいわゆるカンボジア難民が収容されたアランヤプラテートは、この5号線の国境を越えたタイ側にある。
朝食を市場近くの屋台ですませ、コマイさんや前日のドライバーから仕入れた情報を頼りに、乗り合い自動車の発着所を探しに出かけることにした。ぶらぶら歩いて行くと、ガソリンスタンドの向かいに人々のたむろしているのが見える。どうやら、ここらしい。
カタコトの言葉で訊ねると、プレクプヌーという町まで行くという。ぼくが乗ればちょうど満員になるらしく、すぐ出発するから車に乗れ、と言う。
かたわらに、ずんぐりむっくりした1940年代を舞台にしたのアメリカ映画に出てくるような大型のシボレーが止まっている。すでにギューギュー詰めの後部座席に押し込まれ、バタンとドアが閉まった。フロントシートには運転手を入れて4人、リアシートには、ぼくを含めて6人、合計10人の人間を詰め込んで、シボレーは激しくノッキングした後に、走り出した。
国道には1キロごとにプノンペンからの距離を示す里程標が設置してあることが前日わかったので、車の窓から眺めていると、22キロメートルまで読んだところで、最初の町に入った。ここがプレクプヌーの町らしい。市場もあって、きのう行ったコキの町よりにぎやかだ。
露店の中に、肉の塊を板の上に並べて売っている店があった。ふと見ると、肉を並べた台の下に、1匹の犬が寝そべっているのが目についた。ヒモでつながれているわけでもなく、のんびりと昼寝している様子。
肉屋と犬とのとり合わせは〝おもしろい〟と思った。犬の姿が消えたわけではないじゃないか――。急いでカメラをかまえピントを合わせていると、気配を察して犬が目を覚ましてジロリとにらんだ。しゃがみ込みファインダーをのぞいたまま数歩にじり寄ったところで、犬は不快そうに鼻先にシワを寄せ威嚇のうなり声を発してプイと立ち上がり、とことこと歩み去っていってしまった。
ぼくは、恥ずかしかった。
犬の肉かも知れない売り物の肉塊とその下に寝そべる犬――の図を1枚の写真に収めようとするぼくの魂胆を見透かされたようだったからだ。ぼくは、この旅では取材しないでおこうと決めていたはずだったのに。
この旅は、ひたすら“感じる”ことに徹しようと決めていた。だのに、もう、“絵”になりそうな“らしい”場面を探している。きのう、橋のたもとの検問風景を“演出”して撮影していたカメラマンを冷やかに眺めていたくせに、きょうはもう、彼と同じフレームでカメラをのぞきはじめている。犬は、だから怒ったのではないかと、ぼくはその時、思い至ったのだった。
犬が去ったあと、ぼくは気をとり直して人の群れの中に入っていった。
ここでも大人たちは木陰でお茶を飲んでいた。小さな子どもたちは、にぎやかに、ビー玉をして遊んでいた。
少し年かさの少年たちは、ここでもそれぞれM16を手に掲げたり肩にかついだり、いかにも扱い慣れた感じ。三々五々、数人のグループで国道を先に歩いていく。
ぼくも、あっちに行きたいのだが、大丈夫だろうか?
身ぶり手ぶりで訊ねていたら、一人が、腕を取って、こっちへ来いと言いながら連れて行ってくれた。そこには、リヤカーを引いたバイクが何台も客待ちしていた。ホンダ、カワサキ、ヤマハなどの小型バイクが、リヤカーに4~5人の人間を乗せて運んでいる。自動車はここまででオフ・リミット。
荷物をかかえてリヤカーの荷台にうずくまる数人の男女の中に割込ませてもらう。「行くでぇ」と、ひと声かけてバイクが走りだすと、リヤカーは大揺れに揺れる。ふり落とされないように必死でしがみついたまま、2~30分も走ったろうか。
道中、歩いている人たちを大勢、追い越していく。炎天下の街道を、荷物を頭に乗せてゆったりと歩く女性や、自転車に乗っていく青年や、銃を肩にかついで裸足でぞろぞろ歩く少年のグループ……など。もうすぐ〝戦闘地域〟だというのに、街道の、この人通りの多さは何なんだ。
やがて、橋がドサリと落ちているところで、バイクは止まった。
トンレサップ川に注ぐ幅2~30メートルの支流にかかっていた橋が爆破されていた。APCタンクと呼ばれる兵員輸送用装甲車とジープが渡河の順番待ちのため、何台も列をなしている。
小型舟艇をずらりと並べた上に板を敷いて桴をつくり、タンクやジープを1台ずつ乗せては対岸からウィンチで引っ張ってたぐりよせるという作業を繰り返している。桴に便乗して向こう岸にわたり、しばらく歩くと、また橋が落ちている。今度のは流れが細いので路肩から下へ降りてバシャバシャと渉る。
このあたりまで来ると、橋という橋はことごとく爆破されており、道をそれたかつての水田地帯は地面が軟弱なぬかるみ同然で、図体の大きな戦車はほとんど動きを封じられて使いものにならないらしい。
ゲリラの狙いもそこにあるらしく、もう少し先まで歩いていくと、川でもないところで道路がブツブツと切断されていた。ちょうど公園の砂場で、砂を盛り上げてつくった道に直角に手をかけて真横にぐいと一掻きすれば盛り土の道路が掌の幅だけ掻き取られるだろう――そんな具合に、国道の盛り土が掻き取られ分断されている。
あたりに広がる、かつての水田には、すでに雑草がはびこっているのだが、その表面は、まるで思春期の男の子のニキビ面のように穴ぼこだらけ。よく見ると、砲弾が落ちてできたクレーターのようだった。数メートル間隔でボコボコになっており、おびただしい砲弾が射ち込まれたことを物語っている。つまり、このあたりは、つい数日前までは反政府勢力のテリトリーだったのを、政府軍が攻撃して押し戻したということを意味しているというわけだ。
このように、最前線は、首都から20キロメートルラインのあたりを数キロの幅にわたって押したり押し戻されたりしているのが現状のようだった。
――と、そんなことを考えながら、とぼとぼと歩いていると、いよいよ現在の前線に近づいたと見えて、田んぼの中でドンドンと大砲を射っているのが見えだした。
前日の1号線では、初めて見る〝戦場〟に、いきなりバイクで突っ込んでいくという荒っぽいアプローチだったせいで、ぼくもいささか慌てたものだったが、この日は〝馴れ〟もある上に、徒歩でのアプローチなのでいくらか気持ちに余裕ができている。
いま目の前にある大砲は、150センチほどの直径のタイヤ二輪のついた、砲身が3メートルほどの、小型のものだった。
半裸の男たちが汗みずくで発射準備の作業をしているのを、しばらく眺めていたが、誰も咎める様子はない。おそるおそるカメラを取り出して、撮影してもいいかと手ぶりで訊ねると、もっと近づいて撮れとでも言っているらしく、わいわい言いながら手招きしている。オレを撮れ――とポーズをとる者もいて、みんな明るく陽気で人なつこいのには驚いた。
大砲に限らず、武器や兵器についてぼくはよく知らないのだが、こんな物騒な機械をこんなにふざけながら気楽に扱っていいのだろうか。なにしろ、これから発射しようとする砲弾を一本ずつ円筒型のケースから取り出して、ぼんぼん放り投げてよこすのだから恐れ入る。その弾の先端のネジをはずして、その穴に円錐形の信管をねじ込みながら、大砲の脇にどんどん並べてゆく――ともあれ、男たちは鼻唄まじりで準備しているところだった。
10メートルほど離れたところで折りたたみ式のテーブルに地図を拡げコンパスをにらみながら、このチームの指揮官らしき人物が何やら指示を出している。迷彩布でおおったヘルメットをかぶり、階級章のついたシャツを腕まくりし、腰にはピストルをつけ、足元はコンバットブーツ……。こうした本格的ないでたちは彼ひとりきりだった。
好奇心にかられてウロウロしているうちに、大砲に方位と仰角が与えられ砲弾の装填が終わった様子が伝わってきた。
裸の男たちは汗をふきふき木陰に入ってきて、やれやれといった風にタバコを吸い、冗談をとばしてゲラゲラと笑いあっている。
しばらくすると、くだんの指揮官が進み出て腕時計を見ながら声をかけた。言葉は分からないが、「さあ、ぼちぼち始めよか」といった感じ。
そのかけ声を合図に、裸の男たちはノロノロと立ちあがり、軽口をたたきあいながら大砲にとりついた。砲撃開始の雰囲気が漂いはじめた。
どうやって撃つのだろうか、砲手の手元を見ようと思ってぼくは近づいていった。1メートルほど近づいたとき、突然、砲弾が発射された。
………。
音は、聞こえなかった。
そのかわり、まるでビンタをくらったような衝撃を両頬に受けて頭の中が白くなった。
一瞬、なにごとが起こったのか、わけがわからなくなったが、どうやら、発射の衝撃波にもろに襲われたらしい。
反射的に顔をそむけたその視野の中で、付近の水溜りに憩っていた蝶の群が飛び散るのが見えた。何十という数の蝶が紙吹雪のように舞い散った。豊かに繁った大樹の枝がゆさゆさと揺れる。
ぼくの行為がよほどトンマに映ったとみえて、後ろの方で眺めていた兵士の一団がゲラゲラと笑っている。笑いながら、耳を手で押さえろ、とジェスチャーで教えてくれている。そういえば、彼らはみんな手のひらで耳にフタをしているようだった。ただ、大砲のフタを開閉して弾を込める係と引き金のロープを引っ張る係は平気な顔で仕事をこなしているのには驚いた。
不意討ちをくらってすっかり肝を冷やしたので、ぼくは早々に退避することにした。
しかし、その間も、同じ方向を向いて並んだ2門の大砲は休むことなく弾を射ち続け、前もって準備した30発ほどの弾を射ちつくすつもりらしかった。
これまで見てきたいくつかの大砲の脇には、たいてい、にわかづくりの仮小屋がかけられていた。小屋といっても、ちょうどぼくらがキャンプに使う家型テントくらいの大きさだったが、この陣地にも砲弾用の空薬莢を並べた上に板を敷いてバナナの葉を屋根にした小屋ができていた。天井まで1メートルほどしかない、ただ雨露をしのぐだけの簡単なもので、〝ドア〟などというようなものはない。
ひょいと何気なくのぞいてみて、ぼくは仰天した。
なんと、その小屋の中では、赤ん坊がすやすやと昼寝の最中だったのだ。母親が添い寝してバナナの葉をうちわにして風を送っている。
母親は、ぼくと目が合ったとたん“にっ”と笑っただけで、何事もなかったかのように平然と横たわったままだった。
……?
実戦中の大砲の脇で、なんで赤ん坊が昼寝やねん。
なにしろ言葉が通じないので、混乱に陥った頭を整理するのに、だいぶん時間がかかったが、どうやら砲手たちは家族連れで仕事をしているらしかった。
予定量の砲弾を射ちつくしてしまうと、父親が、やれやれという表情で汗をふきふき妻のところへ帰ってきた。
帰ってきて何やら話をしたあとで、彼は、そこに立てかけてあったM16を提げて、ぶらぶらと歩いていく。川のほとりまでついていくと、何人かの10歳前後とおぼしき少年たちが待っていた。兄弟というわけではないようだ。
彼は子どもたちと談笑しながらゴソゴソしていたが、ひと声叫んで子どもたちに注意を与え、ボールのようなものを川にほうり込んだ。ドボンと音がしたように思う。
と、その瞬間、どっと水柱が立ってキナ臭い嗅いがあたりにただよう。彼は、あきれたことに、手榴弾をほうり込んだのだった。
その意味はすぐに分かった。水面のそこかしこに大小の魚が白い腹を見せてぷかぷかと浮かびあがってきた。水際で待っていた子どもたちは、われ先に泥水に跳び込んで魚をかき集め、草むらにポンポンほうり上げる。水の中でふざけあいながら遊んでいるようにも見えるが、どうやら、この魚たちは晩ごはんのおかずになるらしい。この部隊の何家族分ものおかずを調達しているようだ。
この光景を眺めながら、ぼくは、この難儀の中で生き抜くこの人たちの、あきれるほどの順応力と〝したたかさ〟とに、ただただ驚き感心するばかりであった。
最後の大砲陣地を後にして国道を先に進んでいくと、壁を吹きとばされて柱だけになった廃屋の陰で休憩している部隊に出くわした。これは戦闘部隊らしい。
「やあ、こんにちは」
習いおぼえた数少ないクメール語で挨拶すると、まあこっち来て腰かけろや、と、たぶんそう言ってくれているらしいので、かたわらに積んである箱に腰をおろしたのはよかったが、実は、それは弾がギッシリ詰まった弾薬箱なのだった。機嫌よくタバコなど吸ったあとで知らされて、ぼくは跳び上がってしまった。その様がおかしいと言って、みんなは大笑い。それにしても、兵隊たちは、よく笑う。
ぼくが笑い者になっているのを見て、国道のむこう側の並木の根方にたむろしている連中が、こっちに来いよと手招きしている。写真を撮れよと、M16 を構えてポーズする者もいる。
彼らの方に近づいて行こうと、街道を横切っていると、1人の、いかにも軍曹か何か下士官タイプの男がのっそりと立っている。目が合うとプイと顎をしゃくってみせた。「あれを見てみろ」と言いたいらしい。彼の足元には、直径1メートル深さも1メートルほどの丸い穴があって、底に〝何か〟があった。
何か、分からない。
のぞき込んで、よくよく見つめると、その物は半ば白骨化した腐乱死体であることが、わかった。
黒いシャツに黒いズボン。
「フー?」
「ヴィーシー」
「……?」
〈ヴィーシー〉というのは、これまでに何回も聞いたことがあった。クメール人との会話の中でこの言葉は、この内戦の対戦相手、つまり「敵」というぐらいの意味に相当する言葉として使われているようだった。プノンペンのベン・サボラス君に「ヴィーシーというのはエネミーのことか」と訊ねたら、そうだと答えたので、何となくそんなものと思っていたのだが……。
それにしても、ぼくが会ったこの国の人たちで、反政府勢力を「クメール・ルージュ」と呼ぶ人はいなかった。政府軍司令部の将校も、相手を「ヴィーシー」と呼んでいた。
ヴィーシーとはフランス語?と訊ねるといや英語だよ、おまえそんなことも知らんのか、という雰囲気なのだった。
それやこれやで困惑したが、判かってみれば、なんだそんなことか、という始第。つまり、ヴィーシーとはVCであり、「Viet Cong」の略称だったのである。彼らは敵をベトコンと呼んでいたのである。これには驚いた。ベトコンとは「南ベトナム民族解放戦線」の俗称ではないか。それがどうして、クメール共和国政府軍の敵なのか――。
この呼び方の背景やプロセスについての議論は、この内戦の背景とプロセスを象徴的に反映しているので興味深いのだが、ここでは深入りしないで先を急ぐことにする。
いずれにしても、冷たい穴の底で白骨化している死体は、〝敵〟であるらしかった。穴は、埋葬のための墓穴ではなく、〝ヴィーシー〟たちが身を潜めるために掘った、いわゆるタコツボなのだった。この死体はおそらくクメール・ルージュの兵士であり、自ら掘った穴の底にくずおれた――と思われた。
「埋めてやらないの?」とジェスチャーで訊ねてみる。
「ノン」
彼はそう言い捨てて、遠くを見つめた。
その視線の先には密林が広がり、もくもくと黒煙がたち昇っていた。いましがた発射した砲弾の着弾地点からたちのぼる硝煙にちがいない。
タコツボは、街道の路肩沿いに、そこらじゅうに掘ってあった。よく見ると、穴と穴とがトンネルで結ばれている。さらに、そのトンネルは背後の繁みにつながっている。人間一人がかろうじて這い進めるほどのミニトンネル。溝を掘った上に椰子の葉やワラなどでフタをして土をかけ、カモフラージュしてあった。政府軍兵士の手で覆いがあばかれていたので、ぼくもそれと判ったが、そうでなければとても見分けがつかない。〝神出鬼没のゲリラ戦〟の一面を見るようだった。
 |
|
|---|---|
|
ぼくは、穴のひとつに入ってみた。土はひんやりとしていて湿っていた。ゲリラたちはここにしゃがみ込んで、国道5号線を進んでくる政府軍を待ち伏せしていたのか。
地面が目の位置にあった。
そのとき初めてぼくは、あたりの地面が銃弾の空薬莢で覆いつくされているのに気がついた。何千何万というおびただしい数だ。参道に敷かれた玉砂利のように、びっしりと地面をおおっている。サイズもいろいろで、小指大から、子どもの手首ほどの太さのものまで入り混じっている。
カセットテープ大の新品のカートリッジも散乱している。ケースから引き出してみると、10発ほど(ひょっとしたら12発だったかもしれない)ほど並んだ赤銅色の小銃弾が南の国の太陽の光を、にぶく反射する。この新品は、1個の値段はなんぼくらいするのだろう。ああ、もったいない。
もっと値の張りそうな大口径の機関銃弾のベルトも、トグロを巻いたまま放置されている。
これらの多くは、おそらく〝ヴィーシー〟たちが残していったソ連製や中国製のものだろう。政府軍が使っているアメリカ製のも混じっているらしいが、ぼくには見分けがつかない。
いずれにしても、この数日中にこの場所で敵味方入り乱れての相当激しい銃撃戦があっただろうことが、ひしひしと、うかがえる。
半ば呆然として闘いの跡に立ちつくしていると、首都の方から、APCタンクの一団がやってきて、ぼくらの目の前を通り過ぎた。キュルキュルとキャタピラの音、ゴーゴーとエンジンの音、ゴトゴトとキャタピラが路面を噛む音。空薬莢が圧しつぶされる。新品の実弾も……。
ということは、火薬のつまった薬莢が圧しつぶされれば、発火して弾丸が発射されるわけで……。そう思い至ったとたんに、背中を冷汗が流れた。なんと、うかつなことだろう。
いまにも暴発弾が飛んで来そうで、ぼくは立ちすくんだまま金縛りになってしまった。
しかし、タンクはおかまいなしに走り続け、最後の1輛が去っても、何事も起こらなかった。
見ると、キャタピラに圧しひしがれペチャンコに変形したまま、弾丸はそこにあった。薬莢の尻を撃針が打たないかぎり発射しない仕組みになっているのだろうか。いまだに、そのことが不思議でならない。
ひしゃげた銃弾を手にして首をひねっている風がおかしいのか、木陰の兵士たちがまた大笑いしながら、こっちへ来いと言う。そのうちの1人が自分のM16をさし出して、撃ってみろと言っているらしい。
とんでもない。背筋の冷汗もまだ乾いていないというのに、とてもそんなぶっそうな代物にさわる気にはなれないと、日本語で言い訳しながら辞退すると、彼は、いいか見てろよ、という様子でそのライフルを構え、椰子の木の先端を狙って引き金を引いてみせる。〈セミオート〉とかいうらしい撃ち方で断続的に弾が発射されるが、当った様子はない。まわりがドッとはやしたてるので、彼も意地になって撃ち続け、ようやく、椰子の先端がはじけとんだ。
そのうち、別の場所でも数人が撃ち始め、複数の銃声が交錯しはじめた。彼らはトンレサップ川に向かって撃っている。今度は何を的にして遊んでいるのだろうか。まったく呑気な連中だ。
川幅はおよそ2~300メートルか。対岸は、うっそうとした森である。的になりそうなものは見当たらない。
と、その時、対岸の森の暗がりで、一瞬、パッパッと火がまたたいた。何だろうと思う間もなく、ヒュンヒュンと、空気を切り裂くような音がしはじめる。
隣にいた兵士がぼくの肩をたたいて対岸を指さし、ライフルを撃つ真似をしてみせるが、まだ何のことかわからない。
次の瞬間、音が変わった。文字に表せば、グィーンとブーンの中間のような、プロ野球の打者が素振りをするような音だった。
その時になって、ぼくにもようやく事情が呑み込めた。
川の向こう岸から、撃ってきている――。
この音は、至近距離を通過する弾丸が空気を切り裂く擦過音――。
と、思い当ったとたん、突然、足元から恐怖がかけ昇ってきて、頭の中を駈けまわる。
ブンブン、グィーングィーン。耳のすぐそばで音がする。なのに、銃声は聞こえない
対岸の暗がりから誰かがぼくを狙っている――。えらいこっちゃ。居ても立ってもおれない気持ち。こんな時にはどうする? そうだ、地面に伏せなければ。
ぼくは、クモのようにその場に這いつくばった。場所を選んでいる余裕はない。
どれだけの時間そうしていただろうか。
おそるおそる目を上げると、まわりの男たちは、にやにや笑いながらぼくを見おろしていた。ライフルを撃っていた連中は立ったまま。大木の根方でタバコを吸っていた男たちも悠然と煙をくゆらせたまま。
白昼夢から醒めた心地だった。弾に当たらないことを前もって知っていたかのような落ちつきぶりだ。向こうのライフルなり機関銃の射程距離が何メートルくらいのものか、ぼくは知らない。しかし、たとえこの場所が射程外だとしても、あれほどビュンビュン撃たれれば危なくないわけはないのに。
あとで調べると、ライフルや機関銃から発射される弾丸の初速は音速の約3倍らしい。なので、銃声が聞こえる前に弾丸が飛んでくる。その銃声も対岸の森から撃ってくるため、ほとんど聞こえない。銃声から切り離されて弾丸だけが殺到してくる。この恐怖は、ほかにたとえようがない。
“敵”が、川を渡って攻めて来る気配がないからといっても、あの落ち着きようは、何なんだ。彼らは神経がマヒしているのだろうか――。
彼らから見れば、ぼくの怯えようの方が過剰だったらしい。腰ぬけに見えたかも知れない。中の1人が自分のヘルメットと“ちゃんちゃんこ”のような防弾チョッキを差し出して、これを着けろと言ってくれた。
ヘルメットには、弾丸が貫通した穴がポツンとあいている。何だこれは、縁起でもない。
おちょくられているのは判っていたが、せっかくなので、防弾チョッキだけ着けてみる。着けてみると、左の胸にえぐれた痕跡があるのに気がついた。それを待っていたかのように、持ち主の若者が、そのえぐれを示しながら、これはこんな風にしてついたのだと説明を始めた。斜め前方から弾丸が飛んできてそこに当った後、横にそれていったのだと、その弾道をジェスチャーで教えてくれる。ぼくが怯えるのを期待している様子なので、それならこっちも、というわけで、オーバーに怯えてみせながらジャケットを脱いで投げ返してやった。
まわりでまた、ひとしきり、あけっぴろげの笑い声がわき上がった。
ひとしきり笑い会っているちょうどその時、まるでタイミングをはかったように、前線の方から一台のジープがフルスピードで走ってきた。白昼にもかかわらずヘッドライトを点灯している。目の前を走り抜けるジープの幌には赤十字のマーク。幌の中で上下2段に固定された担架には血だるまの兵士が2人横たわっていた。
暗いような明るいような、悲惨なようなのどかなような、緊迫しつつのんびりと、乏しくて豊か、おかしくて哀しい……死の影と生の喜びが同居する、こんな生活空間で1ヶ月を過ごして、ぼくは“無事”に大阪に帰ってきた。
ぼくがあの街を後にしてから10ヶ月後、1975年4月17日に、プノンペンは“陥落”した
終わり
(1992年 南船北馬 NO.13 掲載) |