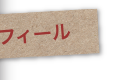「ハンセン病隔離は違憲」との判決が5月10日熊本地裁で出た。特効薬もあり完治することが明らかになり、遅くとも1960年以降隔離政策を用いるほどの特別な疾患ではなくなったのに、国会は「らい予防法」の改廃を怠り(1996年廃止)、厚生大臣も長期にわたって漫然と隔離収容政策を続け、「ハンセン病が恐ろしい伝染病でありハンセン病患者は隔離されるべき危険な存在である」との社会意識を放置したなどとして、国家賠償を命じる判決だった。
私は、1971年にカリマンタン(ボルネオ島のインドネシア領)の奥地でハンセン病の親子が差別されることなく集落の一員として普通に暮らしている家屋に居候させてもらったことがあるのだが、このたびの判決を読みながら、その時のことを思い出した。
南緯3度。ムラトス山脈の辺境にパガランフルという名の集落がある。20メートル四方の高床式家屋一軒が集落を構成し、竹で作ったこの大家屋で集落のメンバー全員が暮らす。ボルネオ北部地域では長屋形式(ロングハウス)だがここでは正方形なのが特徴。竹で編んだ外壁に沿ってロの字状に各家族の部屋が並び、中央部は共同スペースになっている。
私たちの一行5人のなかに医師がいたため、何人もの人が診察を求めてきたが、そのなかに鼻と手の指が失われた母親と頬にひきつれのある息子がいた。
「レプラ(ハンセン病)だ。絶対に接触しないように」と医師は私たちに小声で警告した。
村人によれば、診察を受けるのは初めてとのことらしかった。一段落して、みんなでがやがやと談笑していると、あの母親が、変形した両手に器を挟んでお茶を運んできて、どうぞ飲んでくれという。診察してもらったことに対するお礼の意味を込めた心づくしのもてなしらしかった。
1971年のことである。ハンセン病の感染力がきわめて弱いとは、私も知識としては知っていた。だから、このように一軒の家で大勢が同居しているのに息子一人にしか感染していないのだろうとの推測もできた。そのことが経験的にわかっているから、ここの人たちはこの親子を差別することもなく平気で共同生活をしているのに違いない。マラリアや赤痢・コレラのほうが実はもっと感染力・致死率の高い、恐ろしい病気なのだ。
とはいうものの、私の中の偏見は根強く、彼女の好意のしるしである一杯のお茶を前にして素直に手が出ない。逡巡と葛藤。
同行の医師と軍の連絡将校は、手をつけるな飲むのはやめろと、しきりに目で合図を送ってくる。
これは私にとって一種の踏み絵だと思った。隠蔽されていたアタマとココロのがあからさまにされて私はすくんだのだった。
結局、私は意を決して心づくしのお茶を飲み干し、あと一週間この家に居候したのだが、このときに直面した逡巡と葛藤の体験は、差別するココロの棘として30年たったいまも、忘れられない。
(塾ジャーナル 2001年9月 掲載)