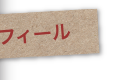アメリカのコロラド州デンバーのたちがアフリカの奴隷を「買う」ために募金活動をしているという話を聞いて我が耳を疑った。なんと、これまでに6万ドルを集めて千人以上も買ったのだと。
いささかショッキングなこのニュースの詳細は分からないままだが、概略は次のようなことだったらしい。
「アフリカのスーダンでは今でも奴隷売買が行われている」という内容の新聞記事を読んだデンバーの小学生の一人が、「それなら、みんながお金を出し合って買い戻してあげればいいじゃないか」と考えたことがきっかけとなって〝募金による奴隷解放運動〟が始まった。そのことがメディアによって全米に紹介されたことから6万ドルの寄付金が集まり、そのお金で1,050名の奴隷を「買い取った」のだそうだ。
いやはや、いかにもアメリカ人らしい発想と行動力だ。小学生の素朴な〝善意〟と〝正義感〟を、大人たちがこのような〝運動〟に仕立て上げたのだろう。
確かに、この小学生の活動は〝美談〟であるに違いない。なのに、どこか何かが引っかかる。喉に刺さった小骨のように、呑み込みをさまたげるのである。
評論家の宮崎哲弥さんが週刊誌(『週刊文集』3月11日号)のコラムで批判しているように、たとえば「先進国の善男善女が買い取りを続ければ、当然奴隷の値段は上昇し、奴隷商は大いに潤う。果ては、本来ならば奴隷にさせられなかった者までが、供給不足、価格高騰のために売りに出されてしまう怖れすらある」というパラドックスが透けて見えるからである。「こういう他者性を欠いた、生半可な同情心は害の方が目立つ」と宮崎さんは書いている。そして、この問題は、さまざまな援助活動やボランティア活動に不可避的につきまとうテーマでもあるのだ。
もうひとつ別の側面もある。「お金を出す」ことが「善行」に直結するストーリーは、大変分かりやすいので、私たちは誰でも参加しやすい。だから、私たち日本人が経済的に〝豊か〟になるにつれてできることが広がった。
たとえば、東南アジアの貧困な子どもの〝里親〟になりませんかという運動がある。応募したその人のお金が特定の一人の子どもの奨学金になるというシステムらしい。私のお金が〇〇という子の奨学金になっているという具体的な実感が持てるからか、多くの日本人が参加しているのは結構なことである。
ところが、私がちょっと引っかかるのは、日本の子どものために里親を探す運動を40年も続けている社団法人家庭養護促進協会への寄付や、実の親に育てられない子を引きとって育てようという里親志願者は、日本が経済的に豊かになるにつれて減少しているという皮肉な現実を知っているからである。
ここにもパラドックスがある。
(塾ジャーナル 1999年5月 掲載)