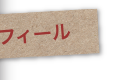日本財団がカンボジアに小学校を100校贈る―という見出しの付いた記事を産経新聞で読んで、感心した。なにしろ100校ですからねえ。たいしたものだ(この金は競艇の収益金の一部らしいが、競馬の儲けは何に使われているのだろうか)。
カンボジアといえば、僕はかつて1974年の雨期に1ヶ月間首都プノンペンで暮らしたことがある。当時は、ロンノル親米政権の末期であり、首都を奪取したポルポト派があの大量殺戮を始める半年前のことだった。
首都を防衛する政府軍のテリトリーは、わずかに半径20キロ圏内だったので、街からバイクで30分も走れば、大砲、迫撃砲、機関銃、自動小銃、手榴弾などがドンパチはじける前線なのだった。
街の中でも爆弾テロや破壊工作が頻々として起っていたので、首都には戒厳令がしかれ、午後6時以後の外出が禁止されていた。
ぐるりをゲリラに囲まれ陸の孤島と化した瀕死の首都をうろついていると、いろいろ不思議なことが見えてくる。
そのうちの一つが、英語塾の大繁盛という現象だ。
文教地区とおぼしき辺りには、小学生クラスから青年クラスまでいろんな種類の英語塾が密集しており、授業が終わった後、子どもたちの群れがふざけあいながら通りにあふれ出てくる様子は、日本で見慣れた光景と変わりなかった。
しかし、こんな時節にどうしてまた英語塾なのか?
街で知り合ったベン・サボラスは、たまたま英語ができるので、複数の塾を掛け持ちで講師をしているのだが、彼の説明によれば、こんな事情があってのことらしかった。
この国は、かつてフランスの植民地だったこともあって、学校制度はフランス式。生徒が習う外国語もフランス語だった。だから国民の多くがフランス語をしゃべることができる。
ところが、戦闘で湯水のように消費される武器弾薬と、戦場になった近郊の田園地帯からの強制疎開者などの流入によって200万人に倍増した人口を養う食糧とを飛行機でピストン輸送するのは、アメリカ合衆国である。政府軍のスポンサーはアメリカなのだ。なのに英語のできる人材が少ない。
ということは、英語ができればアメリカの援助ラインに就くことができる。軍隊に入っても前線に出なくてすむ。そのほか余録も期待できる。
というような解説を早口な英語でしゃべりおいて、じゃ、またあとで、と言いながら彼は慌ただしくホンダ・スーパーカブにまたがり次の教室に向けて走り去った。
いくつかの教室の授業風景をのぞかせてもらったが、いずれもすし詰め状態で大変な熱気だった。
あれから半年後にプノンペンは、陥落した。政権を奪取したポルポトは、英語ができるのは親米インテリの証だとして、処刑リストの上位に名前を乗せるよう指示したという。
(塾ジャーナル 1999年11月 掲載)