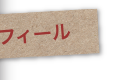戦時中、といっても真珠湾攻撃以後、米英が敵国になったので政府は「敵性語」である英語の使用と教育を禁止した―という話を、戦後生まれ(団塊の世代)の僕たちは、くりかえし聞かされたものだ。
それにひきかえ米国は敵国語の日本語教育を奨励し日系人や文化人類学者を動員して日本語と日本文化の研究を積極的に行わせた。
米国は奨励したのに日本は禁じた→わが国の指導者はそれほど狭量だった→だから戦争に負けたのは当然だ―という三段論法で戦後民主主義が賞揚されるのが決まったパターンだった。
その際、判で押したように「敵性語禁止」の例に挙げられるのが、野球でストライクを「よし」、ボールを「だめ」と言い換えさせられたという「体験談」である。
ではアウト・セーフはどう言ったのか、試合を実況放送する「ラジオ」や「アナウンサー」はどう言い換えたのか、同じように敵性語である中国語やオランダ語は禁止されなかったのかと問うても、「さあ、どうだったかなあ」。記憶にないのである。
でもまあ、多くの戦中時代がそう言っているし、戦争中のことだからそれくらいのことはあったかもしれない。
ところが最近、高島俊男さんがエッセーで3回にわたってこのことにこだわっているのを読んで目からうろこが落ちた。
〈戦中神話とでも呼ぶべきものがある。(略)その最たるものは「英語が禁止されていた」あるいは「英語教育が禁止されていた」という話だ〉(『お言葉ですが…』④文藝春秋)
〈戦争中、英語が各方面で冷遇されたことは事実である。しかし英語教育が禁止されたことはない〉(「『よし』『だめ』の怨念」週刊文春2000年6月29日号)
その証拠に、「ガソリンの一滴は血の一滴」「パーマネントはやめませう」など国策標語、中学校や女学校で英語の授業が行われていたなどの証言、昭和19年4月から使われた文部省の中等学校英語教科書もあるなどの事実を紹介し、「英語教育を禁止していたら文部省が教科書を作るはずがない」と断じている。
野球の「よし」「だめ」にしても、あれは職業野球が時流に迎合して自主的に言い換えたのであって、当時人気の主流を占めていた学生野球ではストライク・ボール、セーフ・アウトとやっていたという当事者の〝証言〟もある。昭和19年2月に封切られた映画「電撃隊出動」に出てきた兵士が野球をする場面でもちゃんと「ストライク」と言っていたという。
職業野球が「よし」「だめ」と言っていたという事実や、勤労動員で授業どころではなったという体験が、いつしか「国によって禁止された」という記憶の創造につながり、〝神話〟になった。
最近の「少年犯罪」をめぐる過去の記憶についても、ぼくには、同様のプロセスがほの見えるのである。
(塾ジャーナル 2000年9月 掲載)