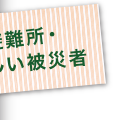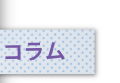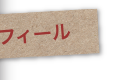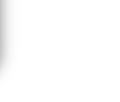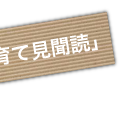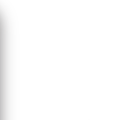


大阪教育大付属池田小学校の2年生と1年生の児童が教室に侵入してきた男に襲われ、8人が死亡した事件については、すでに多くが語られている。子どもたちの群れに鋭利な包丁を振りかざし、手当たり次第に刺し、傷つけ、殺害した男はどのような人物か。理不尽にもいのちを奪われた子どもたちはどのような子どもだったか。マスメディアを通じて多くの〝情報〟が流され、私たちはそのむごたらしさと哀切さに絶句した。なんともやりきれない事件である。
しかし、幼くして逝った子どもたちをいたみ、まがまがしい暴力によっていとしごを喪った親御をなぐさめ傷つき恐怖におびえた子どもたちを癒すどれほどのすべを私たちは持ち合わせているのだろうか。〝こころのケア〟の専門家と呼ばれる人たちが手あてを施してくれていると聞く。目立たないところでは、友人知人隣人など縁ある人々のこころづくしも‥‥。
●私たちの社会は子どもの死に、慣れていない
大多数の子どもたちにとっては〝幸い〟のこの状況はまた同時に、いのちを剥奪された少数の子らへの哀悼と、悲観のきわみにある家族へのほどよいなぐさめのすべを共有できないという逆説をかかえこむことになった。
私たちの世間は、戦後の復興と経済成長のみちすじを「煽(あお)りの文化」のもとにたどることとひきかえに、かつて戦乱や飢餓の時代を通じてつちかってきた「鎮(しず)めの文化」(大村英昭)を捨てたのである。
わが国で、犯罪の被害者として命を剥奪される子どもたちは何人くらいなのか――。不謹慎のそしりを覚悟しつつ調べてみた。
次の数字は「加害によって死亡」した子どもの人数である。(厚生労働省『人口動態統計』)
●煽り文化と鎮め文化のバランスが大切
これには、死因から推測して親子心中の道連れにされた(これも殺人)と思われるケースや虐待による死亡が少なからず含まれている。
さて、犯罪被害で死亡した子どもたちが、多いか少ないか、私はそのことを言いたいわけではない。『煽りの文化と鎮めの文化』とは、社会学者の大村英昭さんの言葉だが、成熟した社会には、この二つの文化装置がバランスよく用意されているものである。江戸時代を眺めてみればそのことがよくわかる。卑近な例をあげれば、たとえば、先人から受け継いだ〝ことわざ〟にもそのことが反映しているのを見ることができる。
善は急げ 急がば回れ
拙速を尊ぶ 急いては事を仕損じる
思い立ったが吉日 待てば海路の日和
まかぬ種は生えぬ 果報は寝て待て
三つ子の魂百まで 死んだ子の歳を数える
左右はほぼ対応しており、左が「煽り系」で右が「鎮め系」と言えようか。しかしながら、近代になってこのバランスが崩れた。近代化と引き換えに私たちは、「鎮めの文化装置」を捨ててきたのである。今や私たちの世間では「煽りの文化」が極度に肥大化し「鎮めの文化」が衰退してしまった。その結果は子育てにも色濃く反映し、早く早く早く、強く強く強く、高く高く高く、‥‥‥、という親の姿勢にあらわれている。したがって皮肉なことに、遅れること、外れること、落ちこぼれることへの親のあせり・不安(「子育て不安」というやつ)がまた肥大することになる。そして最も難儀なことは、この不安や焦りを受け入れ、なだめすかし鎮める働きを用意する文化がやせ細ってしまったことにある。
訓練された「心のケアの専門家」の技術が〝あて〟にされる度合いが強まってきたのは、そうした事情を物語っているのにちがいない。ところで、池田小学校事件の後、混乱のなかで論議されている対応策の一つに「血塗られた校舎だけでなく、体育館も含めたすべての建物を取り壊して新しいものにする」というのがあるが、これはまったく、「リセット」の発想にほかならない。「なかったことにしよう」というわけか。事件を風化させないでほしいと、反対する家族の声もある。〝現実〟に立ち向かうか、折り合いをつけるか、いずれにしてもこの厳しい難問から目をそむけることなく、幼い子らとともに引き受けることこそが、犠牲になった子どもたちの死に報いるべき大人に課せられた課題である。
第Ⅵ巻第7号(2001年7月号)
表1 「加害によって死亡」した子どもの人数 |
||
|
0~4歳 |
|
昭和36年 40年 45年 50年 55年 60年 平成02年 06年 11年 |
293人 304人 321人 379人 234人 150人 86人 89人 64人 |
|