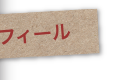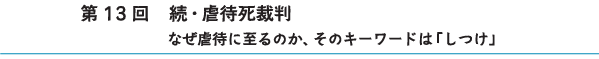
去年の夏(2001年8月)尼崎で、児童養護施設から一時帰宅した小学1年生のわが子(勢田恭一君)を虐待死させ、死体をゴミ袋に入れて運河に捨てた若い夫婦の裁判が進行中だが、その第6回から8回公判まで母親に対する被告人質問がおこなわれたので傍聴に行った。被告(知子・剛士)夫婦は共に25歳。知子被告への質問は合計7時間半に及んだ。その概略を前回に続いて報告したい。
児童養護施設から帰って4日間は平穏だったのに、5日目の夕方から、継父となった剛士被告と実母の知子被告による恭一君に対する折檻がはじまり、思いがけぬ成り行きにお互いが翻弄された結果、8月7日に恭一君は死んだ。夫婦は相談して恭一君の死体を運河に捨て、逃亡した。
事件後メディアが伝えるこの両親の当時の風貌(ヤンキー風)と言動、近所での悪い風評、知子被告の育った家庭と中学時代からの悪い素行などがかぶさって、彼女はでたらめな母親、まったくの同情の余地なし、極悪非道の母親としてのイメージが強化され、非難とさげすみの対象とされた。
しかしながら、法廷で弁護人のみちびきによって彼女が吐露した物語は、また少し違った印象を聞く者に与えたようだった。
被告人の情状酌量を意図した弁護方針もあってのことだろうが、弁護人の質問は6歳で引き取ったわが子を彼女なりにいかにしつけようとしていたのかという点に照準が合わされていた。「しつけ」がキーワードだった。
●きっかけは小さな「うそ」
ぎこちない「家庭ごっこ」の4日間がすんだ後、「しつけ」と「たしかめ」が始まったようだった。きっかけは、恭一君のちいさな「うそ」だった。5日目の夕方、発熱して寝ていた知子被告が起きてみると恭一君の服にカレーの染みが大きくついていたので「それ、どうしたん?」とたずねたら恭一君は「あ、ほんまや」まるでいま気づいたかのようにとぼけた。ゆうべ食べた時のが付いたのははっきりしているのになぜ「うそ」をつくのか。正直に答えなさい、と問いただすと恭一君は「気づかんかった」とか「怒られるから黙ってた」とか、ころころと答えを変えた。その「ええかげんな態度にはらがたったので」彼女は思わずビンタをしてしまった。恭一君は泣きもせず平気だった。
彼女としてはひとこと謝らせたかった。素直にごめんと言って欲しかった。親なんやから。
しかし、恭一君はあっけらかんとして「反省の態度がみられなかった」。こんな素直でない子になったのは前夫の祖母の元での暮らしと施設での生活のせいだ、しつけ直さねば、と彼女は思った。
●「お父さんが一番好き」
一方、継父となった剛士被告は「こいつ、気を遣いながら育ったんやな、のびのびと、欲しいもんはほしいと言えるような生活にしたろ」と言いながらも、恭一君の「本心」を確かめたかったようだった。どこでの生活がいいのか、誰が一番好きなのか、執拗に問いかける。そのたびに恭一君は「おうちがいい」「お父さんが一番好き」と答え続けるのだが、母親と二人きりの時には、本当は学園がいい、学園のS先生が好きと答えていたのだった。
「このうそは見逃せない、その場しのぎのうそはやめさせなあかん」と彼女は思ったという。そのために「剛士も実の子のように怒ってくれるのがうれしかった」とも。
こうして折檻がはじまった。
素直に謝るまで、夕食抜きで壁に向かって正座させる、布団たたきで叩く、武庫川の河川敷に連れ出して、暗闇に放置するなど、やめるきっかけを失ったまま折檻は深夜から明け方まで続いたが、それでも恭一君は「反省した態度」をみせなかった。頻尿と下痢が始まる。
翌日(6日目)は、寝かせようと思ったのにぶつぶつと独り言をいいながら遊んでいたが夜になると「わけのわからないこと」を言いだした。極度の緊張とストレス、睡眠不足による幻聴・幻覚らしいのに、親はこれを「嫌がらせの演技」と受けとって罰を加えた。夜になっても恭一君は眠れなくなっていた。
8月7日(帰宅して7日目)の明け方、ようやく床について夫婦がうとうとし始めたとき突然ふすまを開けて恭一君が入ってきて母親に「何か」を差し出した。うんこで汚れたパンツだった。
「さわるな、クソや」
叫びながら起きあがった剛士被告は恭一君を隣室に連れだした。直後に「座るな」との声がした。
座りかかった恭一君の頭に剛士被告の蹴り足が当たったらしかった。脳内出血。これが致命傷となり数時間後に恭一君は息絶えた。
●一緒に生活していたらわかると思ってた
「恭一君はあなたを実母とわかっていたのでしょうか」被告人質問の最後に裁判長が問いかけたのに対して、知子被告の答えはこうだった。
「口では言っていませんでしたが、一緒に生活していたら自然に肌でわかると思っていました」
恭一君を引きとってからこの親子がともに暮らしたのは合計しても3週間ほど。彼らが暮らした文化住宅は、この法廷から東へわずか300メートルのところにあった。
通巻第80号(2002年8月20日)