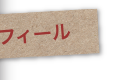紙幣の図柄が再来年、20年ぶりに変わるという。つきものの肖像も、夏目漱石と新渡戸稲造は引退し、千円札は野口英世に5千円札は樋口一葉に交代するそうだが、1万円札の顔は、今後もひき続き福沢諭吉でいくらしい。
●自らの生涯を口述した『福翁自伝』
福沢諭吉。彼のことを知るには『福翁自伝』を読むのが一番だろう。読み物として面白いだけでなく幕末から明治にかけて生きた人の生活史としても貴重な資料となっている。手許にあるのは岩波文庫版(富田正文校訂)。功成り名遂げたあと福沢諭吉は福翁と呼ばれていたので、題名がこうなった。
福沢は明治34年2月、数え68歳で生涯を終えたが、この自伝はその3年前の明治31年(1898年)、65歳のときに速記者をおいて自らの生涯を口述したものなので、文字通りの「物語」、わかりやすく面白い。この中で福沢は一人の父親として自分の子育てについても自慢話を交えながら喋っているので、ちょっとのぞいてみよう。
●九人の子どもの子育て方針
福沢諭吉は天保5年12月12日(1835年1月10日)生まれ。文久元年、28歳で結婚、妻は17歳。その後、文久3年に長男一太郎が生まれたのに続き3男5女をもうけ9人の子ども全員が元気に成長したのが自慢だった。といっても、末子の大四郎が生まれたとき諭吉は50歳になっていたのだが。『学問のすゝめ』というベストセラーの著者でもある彼は、幕末から明治にかけて生まれた9人の子どもを男女の分け隔てなく育てたことを自慢しながら、自分の子育て法について次のように語っている。
「私はもっぱら身体の方を大事にして、幼少の時から強いて読書などさせない。まず獣身を成して後に人心を養うというのが私の主義であるから生まれて3歳5歳まではいろはの字も見せず、7、8歳にもなれば手習いをさせたりさせなかったり、マダ読書はさせない。それまではただ暴れ次第に暴れさせて」犬猫の子を育てるのと変わるところがない。ただ卑劣なことをしたり賤しい言葉をまねたりすると、これを咎めるだけだったという。
100年以上もの昔に、しかも『学問のすゝめ』の著者の口から、このようなことが「私の主義」として語られるとは少々意外な感じがするが、当時の家庭でも子どもには早くから「勉強」させたがる親が普通であり福沢さんはそのような風潮に批判的であったことが次のような「自慢話」からも分かるだろう。
「世間の父母はややもすると勉強々々と言って、子どもが静かにして読書すればこれを賞める者が多いが、私方の子供は読書勉強してついぞ賞められたことはないのみか、私は反対にこれを止めている」
●「早々教授法を改めてもらいたい」
これに関連して福沢さんはとても興味深いエピソードを紹介している。
明治10年に文部省が東京開成学校と東京医学校とを合併して東京大学をつくり、これに付属するものとして東京英語学校を改称した東京大学予備門(後の第一高等学校)を設置したので、福沢さんはちょうどこのころ適齢期になっていた長男(文久3年生まれ)と次男(慶応元年生まれ)をこの予備門(全寮制)に入れ修学させたという。ところが、そのうちに両名とも、「とかく胃が悪くなる。ソレカラ宅に呼び返していろいろ手当てすると次第によくなる。よくなるからまた入れるとまた悪くなる。とうとう3度入れて3度失敗した」というのである。
そこで福沢さんはどうしたか。
かねてから懇意の間柄であった文部大臣の田中不二麿に文句を言いに行った。
「私方の子供を予備門に入れて実際の実験があるが、文部学校の教授法をこのままにしてやっていけば、生徒を殺すに決まっている。……。早々教授法を改めてもらいたい」
この「……」の部分には激しく厳しい学校批判の言葉が並んでいるのだが、差し障りがありそうなのでここには書き写さないでおく。知りたい人は原本でどうぞ。
教科が悪いというのではなく、教授法が悪い、教育の仕様があまりにも厳重で荷物が重すぎると彼は批判しているのである。とはいったものの、いつまで待ってもいっこうに事態は改善せず、福沢さんはついに断念して息子たちに予備門を中退させて、自分が経営する慶應義塾に引き取り、ここを卒業させたあと、明治16年、2人そろってアメリカの大学に留学させてしまった。
●100年前から不登校はあった?
福翁ジュニアのこのケースは、私が知る限りで最も古い「不登校」と「高校中退」の記録といえる。むかしは不登校なんかなかったという俗説を、100年前の福沢親子物語がしっかり否定しているということだ。
通巻第82号(2002年10月10日)