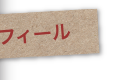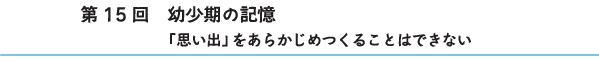
●40年ぶりの再会に不思議な気分
中学時代の同級生の集まりがあるので帰ってこいと世話役の松本次郎から連絡を受けた。中学校を卒業してから、40年になるらしい。
40年? 一瞬わが耳を疑ったものの、指折り数えてみれば、計算は合う。いやはや、いやはやと首を振りながら、隣市に住む諫早修二の車に同乗して5時間、会場に到着すると、30人あまりの54歳の男女が○○ちゃん□□くんと呼び合う世界だった。ぼくにとっては丸坊主とおかっぱだったあのころ以来はじめて会う者が過半数。
一目見て誰それとわかる者といくら見ても声を聞いても全くわからない者とがいる。顔を見ても誰かわからない女の子におそるおそる訊ねて名前がわかったとたん、一瞬にして名前と顔が一致するという面白い体験をした。しばらく時間がたってなじんでくると、いま目の前にいるこの人はどう見ても○○ちゃんなのに、どうしてさっきはまったくわからなかったのか、どうにも不思議な気分だった。
こういう体験の面白さはやはり年をとらなければ味わえないわけで、「老後の愉しみ」になるかもしれない。子どものころ、「何10年ぶりの再会」を大げさに演出するテレビ番組を馬鹿にしていたものだが、あのころの大人の気分がようやく理解できた。北朝鮮から帰還した拉致被害者の人たちが25年ぶりに故郷の同級生たちと再会する様をテレビで見ながら感情移入ができるようになったのもそのおかげだろうか。
●もったいない
20年くらい前、うちの子どもたちがまだ小さかったころのことだが、同じくらいの子どもを持つ友人と、小さな子ども(乳幼児)を海外旅行に連れていくかどうかで議論したことがある。小さな子どもは泣いたりぐずったり手がかかるので旅行の足手まといであるかのように考えられがちだが、ぼく自身のささやかな経験でも小さな子ども連れの旅行者はどこに行っても先々の人々は便宜を図ってくれたり親切にしてくれるものだという印象がある。強行軍で観光地を走り回るパックツアーなどは論外だが、ゆっくり型や滞在型ならむしろ子連れのほうが面白いくらいなものだ。
ところが、ぼくの論議の相手は、とんでもない、もったいないではないか、という。もったいないから自分は子どもが小さいうちは海外旅行には行かないと。
いったい何がもったいないというのか。
「記憶に残らないからだ」
三つ四つまではどこに連れて行っても本人の記憶に残らない。なら、高いお金を使ってしんどい思いをしてまで子連れ旅行するのは無駄である、というのがその男の言い分だった。
記憶として残らないものに投資するのはもったいない(無駄)という発想は、それなりに面白いけど、いささかみみっちくケチくさい考えだともいえる。
●ぼくらの夢には音がでてくる
「幼少期の記憶」で連想されるのが、視覚障害の人たちは夢を見るのか、というテーマである。
1949年生まれのシンガー・ソングライター長谷川きよしは3歳で視力を失ったのだが、見えていたころの記憶はないという。だから、テレビドラマなどで全盲の人の手を取ってべたべたと顔を触らせるシーンがあるけれど、あんなことをしても顔というものを見た記憶がない者にとっては想像ができないのだから、「この人はうっとりするほどの美人だよ」と言葉で説明してくれた方がありがたい、ぼくたちは耳で見ているのだから、というようなことを彼はエッセイ集に書いている。
夢についても書いていて、寝ているときに夢は見るけど、映像は出てこないそうだ。
もう少し大きくなって失明した人はどうだろうか。
花園大学の教員の槇さんは同世代の1948年生まれ、小学生のとき視力を失った。10歳ころまでは普通に見えていたという。
どんな夢を見るか訊ねたら、彼の答えはこうだった。
夢は見るが、映像はない、そのかわり「ぼくらの夢には音がでてくる」のだそうだ。視力を失ってからしばらくは映像の夢を見ていたような気もするが今はまったく映像は出てこないという。見えていたころの映像の記憶そのものがまったくないとのことだった。
子どものために「思い出をつくる」とか子どものための「思い出づくり」とか、気色の悪い表現をこのごろよく見かけるけれど、「思い出」などというものは、他人が計算づくで操作的につくれるものだろうか、よしんばつくれたとしても、親の思い通りにつくられた子どもの思い出などほとんど暴力の産物である。
通巻第84号(2002年12月20日)